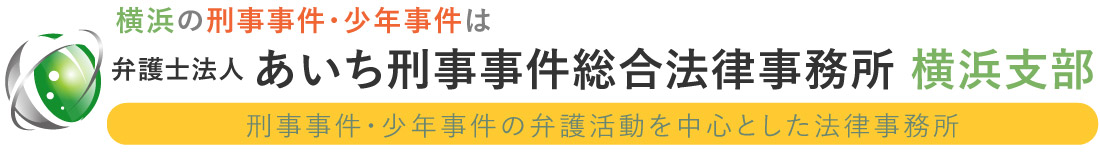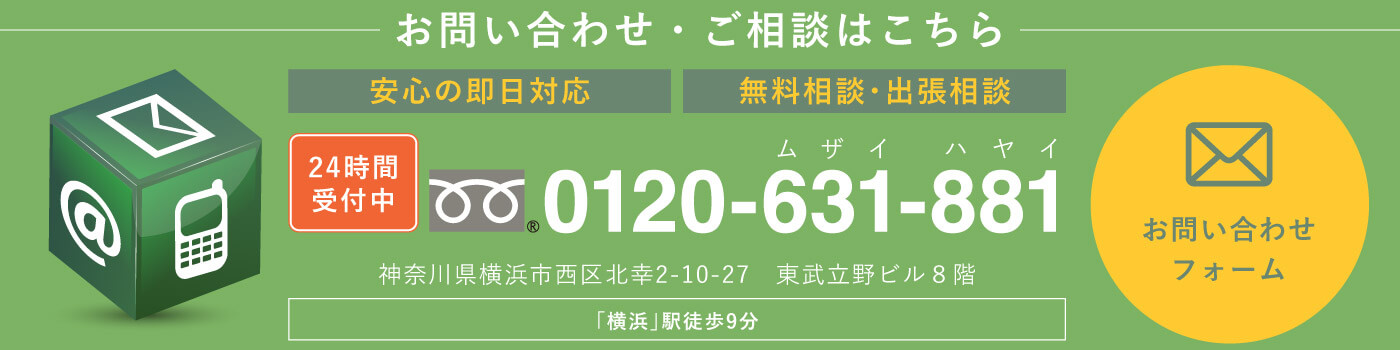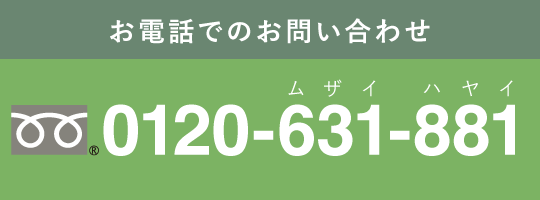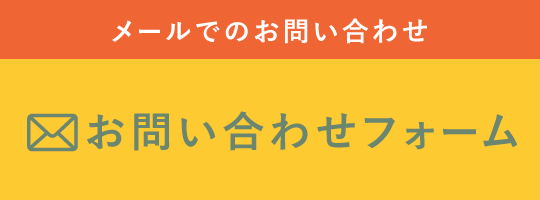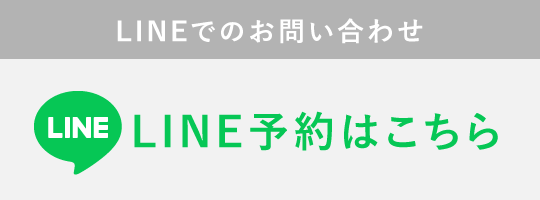Author Archive
神奈川県三浦市のチケット不正転売事件
神奈川県三浦市のチケット不正転売事件
【ケース】
神奈川県三浦市に住むAは、三浦市内の会社に勤める会社員です。
Aは、とあるライブのチケットを転売することで利益を得ようと思い、実際には行くつもりがないにもかかわらず、ライブのチケット10枚(一枚1万円)を購入し、オークションサイトにて一枚2万円を最低限としたオークションを行いました。
結果、10万円で購入したライブのチケット10枚が、計40万円で落札されました。
しかし、チケットを落札者に郵送する前に、不正転売しようとした疑いで警察署から連絡が来て、取調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
【チケットを転売した場合の罪】
ご案内の通り、我が国で開催されるオリンピックの開会式まで、残り1年程となり、盛り上がりをみせているようです。
それに伴い、オリンピックのチケットの抽選申込みが先月までに行われ、来週木曜日に抽選結果が発表される予定です。
今回、オリンピックチケットの販売についての報道に際し、いわゆるチケットの転売対策についても併せて報道されています。
チケットの転売を巡っては、オリンピックに限らず、これまでコンサートやライブなど様々な場面で問題視されていました。
チケットの転売は、一般の消費者がチケットを手に入れにくくしているだけなく、場合によってはそのマージンが反社会的勢力の資金源になっている、とも言われてきました。
これまでも、各地方自治体によっては条例で転売を禁止していましたが、懲役刑が定められている都道府県もあれば罰金・科料しか規定されていない都道府県もあり、中には条例の制定が追いついていない都道府県もありました。
そこで、日本国内で行われる音楽やスポーツのチケット不正転売を統一して禁止するべく、昨年12月14日に議員立法である「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称・チケット不正転売禁止法)が交付され、本日令和元年6月14日から施行されます。
チケット不正転売禁止法は、特定興行入場券(転売禁止が明記されている、当日その会のチケット・指定券である、チケット購入時の名前や連絡先の確認作業を行う等の要件があります。)の不正転売を禁止し、その防止のための措置をとることで、興行入場券の適正な流通を確保することや文化・スポーツ・国民の消費生活を安定させる等のことを目的としています。
チケット不正転売禁止法の定める「特定興行入場券の不正転売」とは、「興行主の事前の同意を得ない特定興行入場券の業として行う有償転売であって、興行主等の当該特定興行入場券の販売価格を超える価格をその販売価格とするものをいう。」と定められています。(同法2条4項)
そして、この法律は「何人も、特定興行入場券の不正転売をしてはならない。」(同3条)「何人も、特定興行入場券の不正転売を目的として、特定興行入場券を譲り受けてはならない」(同4条)と規定しています。
つまり、転売禁止が明記され、そのための措置が講じられているにもかかわらず、チケットの正規の価格より高い値段で転売する、あるいは転売するためにチケットを入手するという行為を禁止しているのです。
この条文に反してチケットの転売や転売のためにチケットを入手した場合、「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と定めています。(同法9条)
ケースのAは、不正転売を目的としてチケットを入手していますので、同法4条に違反する可能性があります。
【略式裁判を求めて弁護士へ】
略式裁判とは、明白で簡易な事件で、100万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満)に相当する事件において、検察官の請求で行われるものです。
本来であれば、検察官が公判請求をすることで公開の法定で裁判を開かれることになりますが、略式裁判は被告人本人が納得して手続き(略受け)をして罰金・科料を納付するだけで事件が完了します。
通常の裁判で有罪判決を受けた場合と同様に、略式裁判であってもいわゆる前科はつきます。
しかし、通常裁判では数ヶ月から数年の時間を要する場合もあるほか、傍聴が可能な公開の裁判で事件についての話をすることを考えると、略式裁判に比べて負担がかかることが考えられます。
よって、通常裁判より略式裁判の方が良いと考えられる方も少なくないでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、施行されたばかりの法律に違反した事件についても対応が可能です。
神奈川県三浦市にてチケットの転売をしたことでチケット不正転売禁止法に違反し、略式裁判について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
神奈川県小田原市で野球賭博②
神奈川県小田原市で野球賭博②
【ケース】
≪詳細については、昨日のブログをご覧ください。≫
神奈川県小田原市に住むAが、X主催の野球賭博に何度も参加していた、という事案です。
小田原警察署の警察官は、Aを常習賭博罪で逮捕しました。
Aの親族は、刑事事件専門の弁護士に逮捕されたAに対する弁護活動を依頼し、野球賭博がどのような罪に当たるのか、野球賭博のような被害者のいない事件ではどのような弁護活動があるのか、相談しました。
(フィクションです。)
【野球賭博に関する罪について】
≪各罪の詳細については、昨日のブログをご参照ください。≫
・単純賭博罪(刑法185条)
・常習賭博罪(刑法186条1項)
・賭博場開帳等図利罪(刑法186条2項)
ケースについて見ると、Aは頻繁に野球賭博に参加しています。
よって、常習賭博罪に当たる可能性があります。
また、「常習として賭博をしていた者」と立証するだけの証拠がなかった場合、単純賭博罪が適用されることも考えられます。
ご案内の通り、単純賭博罪の法定刑は「50万円以下の罰金又は科料(千円以上1万円未満を納付するという刑罰)」であり、常習賭博罪は「3年以下の懲役」です。
常習賭博罪の場合、裁判になって有罪判決を受けた場合、執行猶予が付かない限り刑事収容施設に収容されるということになります。
また、野球賭博を開催しているXについては、賭博場開帳等図利罪が適用される可能性があります。
【賭博罪の例外について】
先述の通り、賭博は「原則」禁止されています。
では、なぜ競馬や競艇、パチンコといった賭け事が堂々と行われているのでしょうか。
時代は戦後、財政上の理由から、「特別法をもって」競輪・競馬・競艇・宝くじ・スポーツ振興投票(toto・BIGといったサッカーくじ)を公認しています。
(例)競馬⇒競馬法、競輪⇒自転車競技法、競艇⇒モーターボート競走法、宝くじ⇒当選金付証票法
※パチンコについては、特別法があるわけではありませんが、風俗営業法2条1項4号に「ぱちんこ屋」として規定されています。
パチンコは風俗営業法のいう「遊技」にあたりますが、遊技の結果に応じて現金又は有価証券を賞品として提供することや客に提供した商品を買い取ることは禁止されています。(風俗営業法23条1項)
また、パチンコの結果に応じて賞品を提供することも禁止しています。(同2項)
そのため、パチンコで勝った人はパチンコ玉を「特殊景品」と交換して、特殊景品を「パチンコ屋とは独立した古物商(景品交換所)」に売って現金を得ます。
そして、古物商は特殊景品をパチンコ屋に売ることで特殊景品がパチンコ屋に戻ってくるという、いわゆる三点方式がなされています。この手法について、今のところ賭博罪の合法性や違法性に言及した裁判例はほとんどありません。
その他、日本人が海外に行ってカジノなどの賭け事をする場合については、違法性が阻却されるとされています。
【贖罪寄付について】
傷害事件や窃盗事件といった「被害者がいる事件」については、示談をするなどして謝罪や賠償を行う弁護活動が考えられます。
しかし、野球賭博のような「被害者がいない事件」や、被害者がいる事件の場合でも「被害者が賠償を拒んでいる」事件については、賠償を行うことが困難です。
そこで、「被害者がいない事件」や「被害者が賠償を拒んでいる」事件では、賠償の代わりに贖罪寄付を行う、という手段があります。
贖罪寄付とは、上記のような場合に、反省などの意思を示す手段として用いられるものです。
贖罪寄付は、日本弁護士連合会や法テラスなどの機関が募っている寄付金です。
贖罪寄付をした場合、贖罪寄付を受け付けた機関から「贖罪寄付証明書」等の証明書が発行され、それを検察官や裁判官に提示することで判断や量刑に考慮してもらう、という仕組みです。
日本弁護士連合会のアンケートによると、贖罪寄付を紹介した弁護士のうち、回答者の8割が情状として考慮されたと回答しています。
【野球賭博などの刑事事件は当事務所まで】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、野球賭博のような被害者がいない事件についても対応しています。
野球賭博をしたことを被疑者が認めているのであれば、身柄解放活動や贖罪寄付などの情状弁護といった弁護活動を丁寧にご説明致します。
神奈川県小田原市にて野球賭博をしたことで常習賭博罪で逮捕され、贖罪寄付をお考えの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県小田原市で野球賭博①
神奈川県小田原市で野球賭博
【ケース】
神奈川県小田原市に住むAは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aは賭け事にさほど興味を持っていたわけではないのですが、小田原市内に住む友人Xから誘われてX主催の野球賭博に参加するようになりました。
Xが開帳していた野球賭博は、プロ野球公式戦を対象に、各球場で行われている試合の勝敗や点数などを当てるという賭け事で、一回の掛け金は数千円から10万円ほどでした。
この野球賭博には数十人が参加しており、公式戦が行われる度に開帳されていました。
そして、Aも頻繁に参加するようになりました。
ある日、Aの自宅に小田原市を管轄する小田原警察署の警察官が来て、「野球賭博の件でAさんを常習賭博罪により逮捕する」と言って、Aを連行していきました。
Aの親族は、逮捕されたAの弁護活動を依頼し、野球賭博がどのような罪に当たるか、また、野球賭博をした場合の弁護活動にはどのようなものがあるのか、刑事事件を専門とする弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【野球賭博に関する罪について】
我が国では、原則として賭博行為を禁止しています。
具体的には、刑法の下記の条文が適用されます。
・単純賭博罪(刑法185条)
「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」
①一時の娯楽に供する物とは何か
一時の娯楽に供する物とは、例えば1回分の飲食費を賭けた賭け事などといった、一時的な娯楽のために消費される物を指し、これは賭博罪の対象にはなりません。
②懸賞や、くじ引き大会、ビンゴ大会、抽選会といったイベントは賭博罪に当たるのか
当事者双方にとって偶然の結果であることが要件になるため、雑誌の懸賞や商店街で行われるくじ引き大会のように、主催者側が一方的に負担を負っている場合には賭博罪の対象にはなりません。
・常習賭博罪(刑法186条1項)
「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」
常習賭博罪は常習的に賭博をしている場合に当たります。
「常習として賭博をした者とは」、反復して賭博行為をする習癖のある者を指します。
実際に常習と言えるかどうかについて、賭博の種類や賭けた金額等を総合的に判断しています。
・賭博場開帳等図利罪(刑法186条2項)
「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」
①賭博場開帳等図利罪とは何か
賭博場開帳等図利罪とは、自分が主催者となって、自身の支配の下で賭博をする場所を開設することを指します。
②営利を目的としていなくても賭博場開帳等図利罪に当たるのか
賭博場を開設することで手数料等の形で利益を得ていて場合はもちろんのこと、営利を目的としていなかったとしても、単に賭博場を開設したがけで、この罪に当たります。
また、賭博場を開設しただけで自分自身では賭博をしていなかったとしても、賭博場開帳等図利罪は適用されます。
③同じ場所に集まって賭博行為をしていない場合、賭博場開帳等図利罪に当たるのか
昭和48年の最高裁判決によると、プロ野球セントラルリーグの公式戦を対象とした野球賭博を行わせるために、とある場所に電話・帳面・プロ野球公式戦の日程表・スポーツ新聞などを備え付け、電話にて賭博の申し込みを受け付け、集計・整理をし、掛け金等の徴収などをした事件で、この管理を行っていた者に対して賭博場開帳等図利罪を適用しています。
【賭博罪の例外について】
≪明日のブログに掲載します。≫
【贖罪寄付について弁護士へ相談】
≪明日のブログに掲載します。≫
神奈川県横浜市中区の常習累犯窃盗事件
神奈川県横浜市中区の常習累犯窃盗事件
【ケース】
神奈川県横浜市中区に住むAは70代の無職です。
Aは家族とも一緒に住んでいて、経済的に厳しい生活を強いられているわけではないのですが、これまでに4回窃盗罪で逮捕され、実刑判決を受けたこともあります。
直近では、2年前に窃盗罪で逮捕され、裁判では「懲役1年6月」の実刑判決を受けました。
それでもAは、横浜市中区内のスーパーマーケットに行き、財布に現金約2万円が入っているにもかかわらず食品を中心に商品7点を、レジを通さずに自己所有のカバンに入れてしまいました。
Aの帰宅後、Aの家族が不審に思いAを問い詰めたところ、Aが万引きしたことを認めました。
Aの家族は、神奈川県横浜市中区を管轄する伊勢佐木警察署へAを自首させたほうが良いのか、弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
【窃盗罪と常習累犯窃盗罪】
ご案内の通り、万引き行為は窃盗罪に当たる可能性があります。
・刑法235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」
通常、万引きをした場合は、この窃盗罪に当たる可能性があります。
しかし、ケースのように、複数回窃盗罪による有罪判決を受けている場合は、常習累犯窃盗罪に問われる場合があります。
常習累犯窃盗は、盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条に規定されています。
・盗犯等ノ防止及処分に関する法律3条「常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル」
カタカナばかりで非常に読みづらい条文ですが、前条に掲げたる刑法各条の罪とは窃盗罪(刑法235条)、強盗罪(刑法236条)、事後強盗罪(刑法238条)、昏睡強盗(刑法239条)を指し、この罪又はこの罪の未遂事件で①常習性が認められ(反復してこれらの罪を犯す習癖がある)、②10年以内にこれらの罪で3回以上、6月以上の懲役刑かその執行猶予付き判決を受けた場合に、常習累犯窃盗にあたることとなっています。
常習累犯窃盗の法定刑は3年以上の有期懲役と定められていますので(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2条)、裁判で有罪となった場合には懲役刑は3年から20年の間で言い渡される可能性があります。
常習累犯窃盗の要件のうち、②(10年以内にこれらの罪で3回以上、6月以上の懲役刑かその執行猶予付き判決を受けた)という部分については、さほど争いがありません。
一方で、①「常習性」については、争いがある場合が考えられます。
例えば、今年の1月に高知地裁が出した判決では、万引きを繰り返したとして常習累犯窃盗罪に問われた被告人に対して、クレプトマニア(後述致します。)を理由に「常習性」を認めず、より法定刑が軽い窃盗罪を適用した裁判例があります。
万引き行為が事実であることを前提に、弁護士としては法定刑が3年以上20年以下の懲役である常習累犯窃盗罪よりも10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が予定されている窃盗罪の適用を目指した弁護活動が必要になります。
【クレプトマニアと弁護活動】
クレプトマニアという言葉をご存知でしょうか。
クレプトマニア(kleptomania、窃盗症)は、お金を持っているにもかかわらず代金を支払わないで万引きをはたらく、あるいは、本当は欲しくない物をついつい万引きする、等といった症状を指します。
クレプトマニアの傾向としては、窃盗を犯すときのスリルや達成したときの快感や満足感を目的としている場合が多いようです。
今日では、都市部を中心にクレプトマニア専門の外来なども設けられており、治療プログラムに参加することでクレプトマニアを克服する方も少なくありません。
クレプトマニアの症状をお持ちの方に対して、懲役刑や禁錮刑を科すことではクレプトマニアの改善は望めず、専門医などによる治療が必要であると言われています。
そのため、クレプトマニアの症状をお持ちの方に対しては、実刑を回避する弁護活動が必要になります。
神奈川県横浜市中区にて、ご家族にクレプトマニアの症状が見られ、実際に万引きをしたことで常習累犯窃盗の罪に問われている方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談をご利用ください。
不正アクセスで保護処分
不正アクセスで保護処分
神奈川県川崎市に住むAさん(17歳)は、日頃から同区内に住む同級生のVさんにからかわれていたため、たまには仕返しをしてやろうと考えました。
そこで、AさんはVさんがよく遊んでいるオンラインゲームのアカウントに勝手にログインし、ゲーム内のアイテムを見境なく削除していきました。
翌日、アイテムが消えていることに気づいたVさんは、高津警察署に不正アクセス被害にあったことを相談しました。
ほどなくしてAさんは不正アクセス禁止法違反の疑いを持たれたため、Aさんの両親は弁護士に保護処分について聞いてみました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
不正アクセスは、他人のパスワードや指紋など(「識別符号」と呼ばれます)を用いたり特殊な操作をしたりして、本来であればアクセス権限がないコンピュータに侵入する行為を指します
日本では「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(通称:不正アクセス禁止法)が定められています。
不正アクセス禁止法は、不正アクセス行為およびそれにつながる行為の禁止や、不正アクセス行為の防止に向けた国や公共団体の義務などを定めています。
不正アクセス行為を行った場合、不正アクセス禁止法違反により3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、AさんがVさんのオンラインゲームのアカウントに勝手にログインしています。
本来ログインに当たってはIDやパスワードが要求され、そうした情報を入力して勝手にログインするのは正に不正アクセス行為に当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は不正アクセス行為に当たることになるでしょう。
更に、仮に不正アクセス行為を通して財産上不法な利益を得た場合、電子計算機使用詐欺罪が併せて成立余地が出てきます。
そうなると、事件の重大さは当然高まり、処分は相応に重くなることが見込まれるでしょう。
【少年事件における保護処分】
少年(20歳未満の者)を被疑者とする刑事事件は、少年事件として通常の刑事事件とは異なる手続が行われます。
少年事件の最大の特徴は、通常の刑事事件のように刑罰が科されるわけではなく、少年事件に特有の保護処分というものが行われる点だと言えます。
通常、少年というのは心身共に未熟であり、自己の行いの重みを認識することなく非行に及ぶことがよくあります。
そこで、刑罰による制裁・矯正よりも、少年の健全な育成に向けた適切な取組みが行われるというわけです。
少年に対する保護処分の要否と内容は、少年事件を専門の一つとする家庭裁判所で決定されます。
保護処分には、①保護観察、②児童自立支援施設・児童養護施設送致、③少年院送致の3つがあります。
これらの保護処分を行う必要がない場合は、審判不開始あるいは不処分として何らの処分を行われないことがあります。
以下では、実務上よく対比されることもある保護観察と少年院送致について見ていきます。
①保護観察
保護観察官および保護司の指導・監督のもと、他の施設に行くことなく自宅などで更生を図る処分です。
少年院などの施設に行かずに行うため、基本的には両親をはじめとする家族の監督下で更生を目指すことになります。
それと並行して、保護司や保護観察官から適宜生活指導を受けることもあります。
③少年院送致
自宅などを離れて少年院に収容し、更生に向けた指導・教育を受けさせる処分です。
少年の中でも特に要保護性が高い者に対して行われるもので、少年の性格や非行などに応じて更に細かく分かれます。
世間一般のイメージもあり、少年院だけは避けたいというご要望が多いのは事実です。
以上で見たように、保護処分は少年ひとりひとりに応じて適切なものが選択されるものであり、いずれが適切かは各少年により異なってきます。
選択される保護処分の見通しも個々の事案により異なってくるので、もし何かお悩みであれば弁護士に相談してみるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に詳しい弁護士が、保護処分を含む少年事件のポイントをしっかりとお伝えいたします。
お子さんが不正アクセスをしてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
落書きで建造物損壊罪?
落書きで建造物損壊罪?
Aさんは、神奈川県内をバイクで散策しては、道路の設置物やトンネルなどにラッカースプレーで落書きをしていました。
ある日、Aさんが神奈川県足柄上郡内の公園にある公衆トイレの壁に落書きをしていたところ、その様子をたまたま通行人のWさんに目撃されました。
Aさんは、Wさんから「落書きは犯罪だよ。松田警察署に通報したからね」と言われ、慌ててその場を立ち去りました。
後日、Aさんは自身が逮捕されるのではないかと思い、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(上記事例はフィクションです)
【落書きに成立する罪】
外を歩いていると、たとえば歩道橋やトンネルの壁などに落書きがされているのが目に入ります。
落書きはその場所にすっかり溶け込んでいることもあり、落書きという行為につい寛容になりがちです。
ですが、建造物や道路の設置物に落書きをすると、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
まず、考えられるものとしては軽犯罪法違反が挙げられます。
軽犯罪法1条33号は、「みだりに他人の家屋その他の工作物…若しくは標示物を汚した者」を拘留または科料に処するとしています。
街中で見かける落書きは、スプレーやチョークなどで工作物等を汚す行為に当たると考えられます。
そうすると、上記事例のAさんも軽犯罪法違反に当たる可能性があります。
ただ、拘留は1日以上30日未満の拘置、科料は1000円以上1万円未満の金銭の納付であり、数ある罪の中ではごく軽いものと言えます。
場合によっては、軽犯罪法違反ではなく建造物損壊罪が成立する余地もあります。
建造物損壊罪における「損壊」とは、建造物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
このことから、落書きにより目的物を汚損した場合でも、「損壊」に当たるとして建造物侵入罪に当たることはありえるということになります。
上記事例では、Aさんが公園の公衆トイレの壁にラッカースプレーで落書きをしています。
落書きをしたからといって、公衆トイレの壁が崩れたり薄くなったりするというのは起こりません。
ですが、公園という空間を構成する公衆トイレの壁が汚損されたことで、その公園が有する美観が害されるということは生じます。
そうすると、Aさんは建造物損壊罪として5年以下の懲役が科される可能性があるのです。
【逮捕の可能性】
刑事事件と聞くと逮捕をイメージされる方は多いかと思いますが、実際のところ逮捕が行われるケースというのは全体の4割程度です。
そうした逮捕を伴う事件は身柄事件と呼ばれ、逮捕を伴わない事件は在宅事件と呼ばれます。
ニュースなどでよく聞く書類送検というのは、逮捕が行われないことで事件の記録だけが検察庁に送られることを指し、在宅事件に特有の用語と言えます。
ある事件で逮捕を行うかどうかは捜査機関次第であるため、逮捕の可能性について確実なことは言えません。
一応の目安を判断する要素としては、事件の重大性が挙げられます。
事件が重大かどうかは、犯した罪の重さ(法定刑)、被害の程度、犯行の悪質性などの様々な要素に基づき判断されます。
ただ、一般的には、重い罪であればあるほど逮捕の可能性が高まるといってよいでしょう。
たとえば、殺人事件を在宅で進めるというのはおよそ考えられず、被疑者が特定できた段階で逮捕を行うのが通常だと思われます。
逆に、軽い罪を犯しても逮捕の可能性は高くないと思われますが、それでも0になるということはおそらくありません。
絶対に逮捕されないと言い切ることができないのは歯がゆいものです。
もし自身のケースで逮捕の可能性がどの程度か不安に思ったら、ぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、逮捕の可能性や心構えについて丁寧にご説明します。
落書きが発覚したら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
公務執行妨害罪で無罪主張
公務執行妨害罪で無罪主張
神奈川県大和市在住のAさんは、深夜に近所の公園付近を歩いていたところ、大和警察署の警察官に声を掛けられました。
目的は職務質問のようでしたが、警察官はAさんを不審者と決めかかって質問を行い、遂にはAさんが持っていた鞄を無理やり奪い取りました。
警察官は鞄のチャックを開けて中に手を入れたため、Aさんはそれを制止しようと鞄を掴んで強く引きました。
すると、警察官から「公務執行妨害罪だ」と言われ、現行犯逮捕されて警察に連行されてしまいました。
接見で一連の流れを聞いたAさんの弁護士は、今回の件で公務執行妨害罪が成立せず、無罪の主張ができるのではないかと考えました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を行う際に暴行や脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
典型的なケースだと警察官を相手方とするものが思い浮かびますが、公務員であればその他にも様々な者が対象となりえます。
たとえば、私立病院に勤務している医師を相手方とするものもあれば、公務員の補助をする非公務員の民間人を相手方とするものもあります。
公務執行妨害罪は、国または公共団体の事務の円滑な遂行を妨げる点で違法だと考えられています。
そのため、暴行・脅迫の程度がさほど強くなくとも、公務の円滑な執行を妨げるおそれがあったとして公務執行妨害罪となる可能性があります。
上記事例においても、鞄を取り返そうとするAさんの行為が公務執行妨害罪における「暴行」と捉えられる可能性はあると言えます。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
更に、仮に暴行により公務員に傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪だけでなく傷害罪が成立することもあります。
これは、人の身体の傷害が公務執行妨害罪に当然に含まれるとは言えず、傷害罪として別個に評価すべきだという考え方によるものです。
その場合、傷害罪の法定刑である15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれが生じてきます。
【違法な公務と無罪主張】
上記事例の警察官は、Aさんの鞄を奪い取ってチャックを開け、中に手を入れて物色しています。
警察官は犯罪を予防する一般的な責務を負っていることから、職務質問やそれに付随する所持品検査を行う権限が認められています。
しかし、そうした活動は、よほど軽微でない限り対象者の同意がなければできず、強制的に行うのであれば捜索許可状などの令状を要するところです。
そうすると、警察官によるAさんの鞄の物色は、本来行うことが許されない違法な捜査に当たる可能性があります。
以上を踏まえると、Aさんは公務執行妨害罪が成立せず無罪になる余地があると言えます。
その理由は、公務執行妨害罪の性質にあります。
先ほど説明したように、公務執行妨害罪は円滑な公務の執行を保護するために定められたものです。
しかし、国家が刑罰を科して人権を侵害することの重大さに鑑みれば、違法な公務まで公務執行妨害罪による保護の対象にすべきではないと考えられます。
こうした考えから、公務執行妨害罪が成立するのは、飽くまでも暴行・脅迫の対象が適法な公務の場合に限られるとされているのです。
ただし、そもそも無罪の主張というのは容易に受け入れてもらえませんし、警察官を相手方とする公務執行妨害罪については尚更です。
もし無罪の主張をお考えなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してきちんと弁護活動をしてもらいましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の名に恥じない弁護士が、無罪の獲得に向けて知識と経験を総動員します。
ご家族などが無罪にもかかわらず公務執行妨害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件
神奈川県横浜市泉区の覚せい剤取締法違反事件
【ケース】
神奈川県横浜市泉区在住のAは、海外旅行中に知り合った友人を通じて覚せい剤を密輸入し、横浜市泉区内の路上で販売していました。
ある日、Aの自宅に厚生労働省地方厚生局麻薬捜査部の麻薬取締官が来て、Aを逮捕しました。
(フィクションです。)
【覚せい剤の営利目的輸入について】
当然のことながら、無許可者による覚せい剤の輸入は法律で禁止されています。
覚せい剤を営利目的、すなわち、覚せい剤を販売する目的で輸入した場合、下記の法律に反する可能性があります。
・覚せい剤取締法違反
覚せい剤取締法13条では、「何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない」と定められています。
これに反して、営利目的で日本に覚せい剤を密輸入した場合は、覚せい剤取締法41条2項により「無期若しくは三年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは三年以上の懲役及び一千万円以下の罰金に処する。」と定められています。
・関税法違反
我が国に輸入してはいけない物を輸入する行為は、関税法に違反する可能性があります。
関税法110条1項では、「次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」として、その1号で「偽りその他不正の行為により関税を免れ、又は関税の払戻しを受けた者」と定められています。
【黙秘権について弁護士に相談】
黙秘権という言葉は、小説やドラマなどで聞いたことがある方も多くおられる事と思います。
憲法38条1項では、「何人も、自己に不利益な供述を強要されない。」と定められています。
刑事訴訟法では、更に具体的に規定されており、例えば取調べにおける黙秘権については「…取調に際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨をあらかじめ告げなければならない」と規定されています。(刑事訴訟法198条2項)
歴史的に、取調べにおいて、時には取調官が被疑者の自白を引き出すために拷問を行い、時には自白を過信して冤罪を生むといったことはしばしありました。
戦後日本においても、黙秘権を行使できない状況下でなした自白が冤罪を生んだ可能性が高い事件は実在します。
例え弁護人であっても同席ができないとされている我が国の取調べにおいて、黙秘権をしっかりと理解して取調べに望むことは重要です。
その取調べについて、確かに、被疑者(容疑者)は取調べ前に取調官から黙秘権についての説明を受ける決まりとなっています。
しかし、実際の取調べでは取調官の方もあの手この手で情報を引き出そうとする中で、何をどこまで話し、その内容を黙秘すればいいのか、という疑問は常に残ることでしょう。
また、形式上黙秘権が認められていると説明する一方で、「こんな話で黙秘権を使った人はこれまでいなかった」「黙秘権を使うなら勾留が長引くだろうね」などと、ともすれば黙秘権を否定するような話しぶりをする取調官がいることも現実です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
これまで、逮捕・勾留された方の取調べについて、数多く対応して参りました。
当事務所の弁護士は、身柄を拘束されている被疑者(容疑者)の下へ頻繁に接見に訪れます。
弁護士接見では警察官の立会いなしで話をすることが出来ますので、取調べで聞かれた内容や話した内容をしっかりと確認し、毎回アドバイスを行います。
更に、接見で伺ったお話の中で不適切な取調べがあった場合、早急に抗議や異議申し立てを行う必要があります。
神奈川県横浜市泉区にて、ご家族が覚せい剤を営利目的で輸入したことで逮捕され、黙秘権を行使していると聞き弁護士をお探しの方がおられましたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービス(有料)をご利用ください。
神奈川県横浜市南区のストーカー事件②
神奈川県横浜市南区のストーカー事件②
【ケース】
神奈川県横浜市南区にて、Aが好意を持ったVに対し、拒まれたにもかかわらず約120回も電話をかけたり、Vの住むアパートの周りをウロウロしたりといった行為を繰り返す事件です。
Vは禁止命令等を申し出て、禁止命令等が下されましたが、それでもつきまとい等を繰り返したAはストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)違反で逮捕されました。
(フィクションです。)
【つきまとい等・ストーカーへの対応】
昨日付のブログにて、「ストーカー行為=つきまとい等を反復して行う」というご説明を致しました。
以下では、ストーカー被害に遭った場合に警察官がどのような措置を講ずることができるのか、ご案内します。
・警告
ストーカー規制法4条1項では、警察本部がつきまとい等に対しての警告を求める申し出を受けた際、実際につきまとい等が行われていて今後もそれが反復される恐れがある場合には、それ以上反復してつきまとい等を行わないよう「警告」が出来ると定められています。
・禁止命令等
各都道府県の公安委員会は、ストーカー規制法3条に規定されている行為があった場合につきまとい等を反復してする恐れがあると認められる場合には、被害者側の申し出や職権により、①さらに反復してつきまとい等を行ってはならないこと、②さらに反復してつきまとい等が行われる事を防止するために必要な事項、を命じることが出来ます。(ストーカー規制法5条1項各号)
これは禁止命令等と呼ばれます。
禁止命令等をするためには、原則として先に被疑者側(加害者側)の意見を聞く必要があります。(ストーカー規制法5条2項)
ただし、緊急の必要性がある場合には、先に禁止命令等をしたうえで、その後15日以内に聴聞を行うということもできます。
禁止命令等の効力は原則1年ですが、被害者側からの申出や職権により、1年ごとに更新することも可能です。
【ストーカーをした場合の罰則規定】
これまで見てきたストーカー行為ですが、この法律に違反してストーカー行為をした場合は刑罰に処される可能性があります。
ストーカー規制法18条では、「ストーカー行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」と定められています。
ただし、先述の禁止命令等に違反してストーカー行為やつきまとい等を行った場合は、この限りではありません。
ストーカー規制法19条1項では、「禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。」と定められ、同2項では「前項に規定するもののほか、禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同項と同様とする。」と定められています。
【ストーカーで示談】
ストーカー事件では、被害者がいることから、弁護活動の一つに示談交渉が考えられます。
示談交渉は、被害者側が代理人弁護士をつけていない場合は基本的に被害者と直接行う必要があります。
しかし、ストーカー行為をした被疑者(加害者)が被害者と直接示談交渉を行うことは、現実的ではありません。
そこで、弁護士が間に入り、示談交渉を行うことが有効と考えられます。
ストーカー事件のような刑事事件で示談をすることができれば、検察官が被疑者(加害者)を起訴する可能性は低くなります。
また、金銭的な賠償をすることで、被害者の早期救済が望めるだけでなく、被疑者(加害者)にとっては民事訴訟を回避するというメリットもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、ストーカー規制法違反事件をはじめとする「被害者がいる事件」で数多くの示談交渉を行って参りました。
神奈川県横浜市南区にて、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕され、示談交渉をお望みの方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による初回接見サービスをご利用ください。
神奈川県横浜市南区のストーカー事件①
神奈川県横浜市南区のストーカー事件①
【ケース】
神奈川県横浜市南区に住むAは、横浜市南区内を中心とした運送業のアルバイトをしています。
ある日、Aが配達のために横浜市南区内のマンションを訪ねたところ、Aの好みのタイプの女性Vが受け取りのために玄関先に出てきました。
AはVに好意を抱き、配達時に利用するラベルに記載されているVの個人情報を勝手に見たうえで、Vに電話をかけました。
電話を受けたVは、配達をしていたAからの連絡と知り、自宅を知られて気持ちが悪いと思い「電話してこないでください」といって切りました。
それでもAは、朝晩構わず、計約120回Vに電話をしたほか、Vの住むアパートの周りをうろつくなどしました。
困ったVは、神奈川県横浜市南区を管轄する南警察署の警察官に相談し、被害届を提出しました。
南警察署の警察官はAの行動を確認したところ、ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為であると判断し、Vに説明しました。
そこでVは、ストーカー行為等の規制等に関する法律に基づく禁止命令等の申し出を行い、Aに対する禁止命令等が下されました。
それでもAはVに対する連絡やアパートの周りをうろつく行為を止めなかったことから、南警察署の警察官は、Aを逮捕しました。
Aの家族は、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反の場合に示談が可能なのか、刑事事件を専門とする弁護士に無料相談しました。
(フィクションです。)
【ストーカー規制法について】
ストーカーという言葉は、広く一般に利用されている言葉です。
法律上ストーカー行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(通称、ストーカー規制法)によって何がストーカー行為に当たるか定義され、ストーカー行為を禁止されています。
ストーカー規制法は、平成11年に埼玉県桶川市で発生した桶川ストーカー殺人事件(被害女性が交際中の相手に別れ話をしたところ逆上され、ストーカー行為を繰り返された上に殺人事件に発展したという事件。)を契機に、議員立法によって成立されました。
【ストーカーの定義について】
ストーカー行為とは「同一の者に対し、つきまとい等…を反復してすることをいう」と定められています。(ストーカー規制法2条3項)
そして、「つきまとい等」の定義についてはストーカー規制法2条1項にて以下のような内容の規定をされています。
特定の人に対する恋愛感情や行為の感情、あるいは恋愛が成就しなかったことによる逆恨みのような目的で、行為を抱いた相手やその配偶者、家族等の関係者に対して、下記のようなことをすることを指すとしています。
①(1)つきまとい(2)待ち伏せ、(3)住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近での見張り、(4)住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
②行動を監視していると思わせるような事を言ったり、実際に知り得る状態に置いたりすること。
③面会、交際など、義務のないことを強要すること。
④著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
⑤(1)無言電話(2)拒否された後も何度も電話をかけたりFAXを送信したり、電子メールの送信等をすること。
⑥汚物、動物の死体など、極めて不快あるいは嫌悪感を催すような物を送付したり、そのような物が見える場所などに置いたりすること。
⑦名誉を害することを言う等のこと。
⑧(1)性的羞恥心を害することを言う等(2)性的羞恥心を害する文書や絵、DVDやBD、データ等といった物を送付する等(3)(2)のデータ等を送信する等。
≪明日のブログに続きます。≫
« Older Entries Newer Entries »