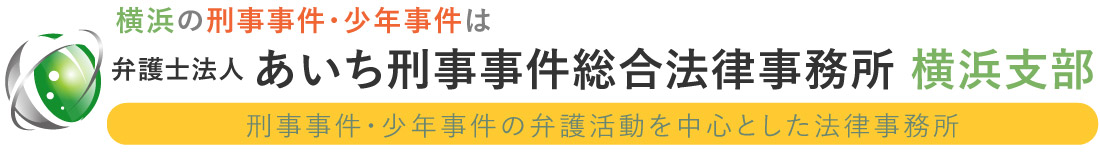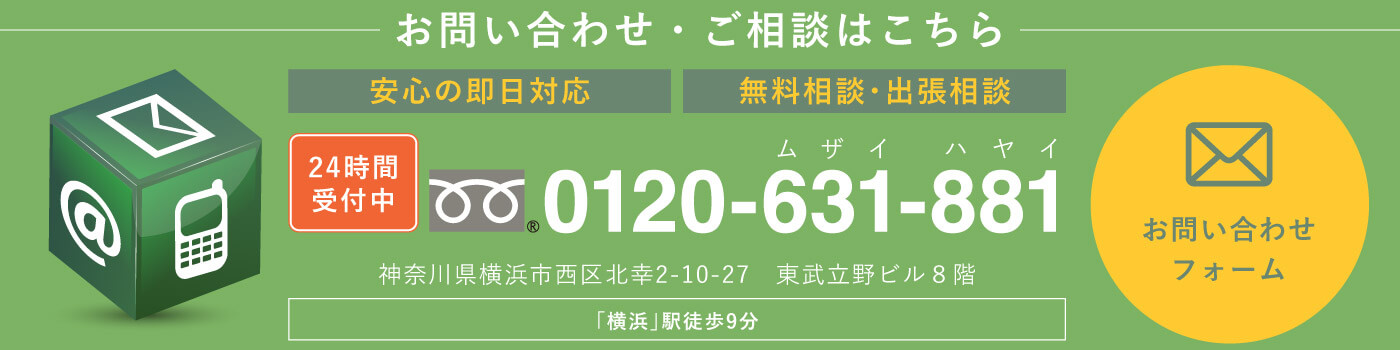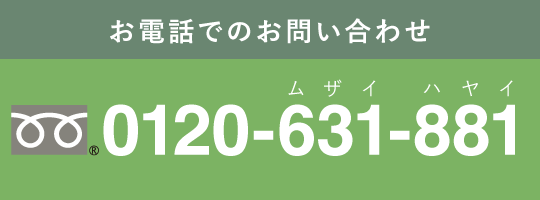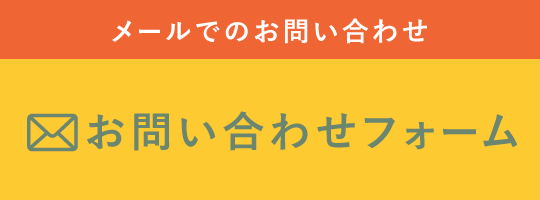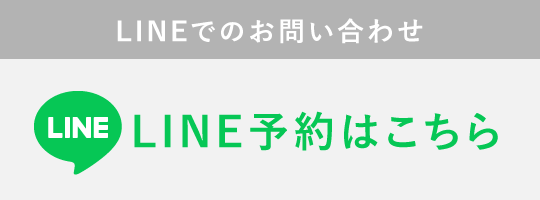Archive for the ‘性犯罪事件’ Category
【報道解説】神奈川県横浜市の性犯罪の同種前科がある事例と執行猶予判決
【報道解説】神奈川県横浜市の性犯罪の同種前科がある事例と執行猶予判決

盗撮等による性犯罪において同種前科による刑事罰への影響について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
2023年に、神奈川県横浜市内の小学校の教室で女子児童の着替えを盗撮し、性的姿態等撮影などの罪に問われた元講師の男性の裁判で、横浜地方裁判所は2024年5月16日に、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
判決などによると、元小学校講師の男性(23歳)は、2023年10月中旬から12月上旬までの間に、当時勤めていた横浜市内の小学校の教室で、女子児童の着替えをペン型のカメラで盗撮するなどした。
16日の判決公判で、裁判官は「立場を悪用した犯行は悪質で、身勝手な動機」と指摘した。
一方で、本人がカウンセリングの受診など再犯防止に向けた取り組みを行っていることや、反省の態度を示していることなどを考慮し、男性に懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡した。
(令和6年5月17日に配信された「奈良テレビ放送」の報道について、犯行場所や管轄裁判所等の事実の一部を変更したフィクションです。)
【盗撮による性的姿態等撮影罪の刑事処罰とは】
ひそかに、人の性的な部位や、人が身に着けている下着を盗撮した場合には、性的姿態撮影等処罰法の「性的姿態等撮影罪」や、あるいは各都道府県の「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けます。
性的姿態等撮影罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金」とされています。
・性的姿態撮影等処罰法 2条1項1号
「正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(略)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(略)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(略)又は人が身に着けている下着(略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(略)がされている間における人の姿態」
【同種前科による刑事罰への影響】
同種前科とは、再犯事件を起こした場合に、以前に同じような種類の犯罪を起こして刑事罰を受けていることをいいます。
再犯事件の裁判において、同種前科があるという事情は大きく考慮されて、刑事罰の量刑の判断が厳しくなります。
同種前科があれば、執行猶予についても、付される可能性は低くなると考えられます。
初犯においては、執行猶予の付されやすい犯罪内容であったとしても、再犯を繰り返せば繰り返すほどに、刑事罰の量刑は重くなり、執行猶予は付され難くなります。
同種前科で量刑が重くなる理由は、本人の反省が見られないことや、本人の犯罪に対する規範意識の欠如、累犯性、常習性が大きく考慮されるところにあります。
刑事事件に強い弁護士に、同種前科のある再犯事件を起こしたことについてご相談いただければ、弁護士の側から、再犯事件の犯行態様や、再犯事件を起こすに至った原因などを、具体的な事件証拠をもとに本人に有利な形で主張することで、できるだけ刑事処罰の量刑を減らすよう働きかけ、執行猶予付き判決の獲得を目指した弁護活動をいたします。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。
神奈川県横浜市の盗撮事件等の性犯罪でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
【報道解説】神奈川県川崎市多摩区の不同意性交等罪の逮捕事件
【報道解説】神奈川県川崎市多摩区の不同意性交等罪の逮捕事件

不同意性交等罪の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
令和5年7月14日、神奈川県川崎市で、知人の女性を暴行し同意なく性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで19歳の男子大学生が逮捕されました。
神奈川県警多摩警察署によりますと、男子大学生は、14日午後7時すぎ、川崎市多摩区内で、知人の10代女性が拒否しているにも関わらず暴行し、同意なく性行為に及んだ疑いが持たれています。
調べに対し、男子大学生は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(令和5年7月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【刑法改定:不同意性交等罪の新設】
令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。
不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。
【不同意性交等罪とは】
本ブログでは、主に不同意性交等罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。
不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。
「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
改定前の強制性交等罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。
今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑となっています。
【不同意強制性交等罪の刑事弁護】
今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。
示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。
性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい逮捕された場合にはどのような罪に問われる?
神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい逮捕された場合にはどのような罪に問われる?

神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしてしまい取調べを受けているという事例を想定して、弁護活動や示談交渉について弁護士法人あいち刑事総合法律事務所横浜支部が解説致します。
【ケース】
神奈川県相模原市緑区在住のAさんは、相模原市緑区の会社に務める会社員です。
Aさんは事件当日、相模原市緑区の駅構内でトイレの個室に忍び込み小型カメラを設置しました。
トイレを利用したVさんが小型カメラに気づき、警察に通報したことで、相模原市緑区を管轄する相模原北警察署の警察官が捜査を開始し、Aさんによる犯行であると認め、Aさんを盗撮による性的姿態等撮影罪で通常逮捕しました。
《ケースはすべてフィクションです。》
【盗撮で問題となる罪】
性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律
第2条第1項 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
1号 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態
2号 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
3号 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
4号 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
第2項 前項の罪の未遂は、罰する。
第3項 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。
神奈川県迷惑行為防止条例
第3条第3項
何人も、人を著しく羞恥させ、若しくは人に不安を覚えさせるような方法で住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服等の全部若しくは一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を見、又は、正当な理由がないのに、衣服等の全部若しくは一部を着けないで当該場所にいる人の姿態を見、若しくはその映像を記録する目的で、写真機等を設置し、若しくは人に向けてはならない。
今回のAさんの事例について、Aさんはトイレでのいわゆる盗撮をしたことで逮捕されました。
盗撮については、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(性的姿態撮影等処罰法)または各都道府県の定める迷惑防止条例に違反します。
まず、性的姿態撮影等処罰法について、これは2023年に新設された法律で、スカートの中やトイレなどの盗撮、あるいは性的な行為や性行為を撮影した場合などに成立する罪で、性的姿態等撮影罪と呼ばれています。
次に、各都道府県の定める迷惑防止条例の問題について、これは2023年の性的姿態撮影等処罰法の施行以前からあるものです。
Aさんの場合は神奈川県相模原市緑区にて盗撮事件を起こしたことを想定していますので、神奈川県迷惑行為防止条例に違反すると考えられます。
【盗撮~性的姿態等撮影罪について~】
性的姿態等撮影罪は、
・正当な理由がなく
・性的な部位や性的な行為を
・密かに撮影する
場合に成立します。
また、いわゆる盗撮ではなくても
・突然撮影をしたり、酒に酔うなど意識がはっきりしない状況での性的な撮影
・16歳未満の性的な撮影
については、性的姿態等撮影罪が成立します。
また、未遂(被害者がカメラに気付いたりカメラがうまく作動しないなど実際には盗撮に至らなかった場合)も処罰されます。
【盗撮~迷惑防止条例違反について~】
盗撮は、従来どおり各都道府県の定める迷惑防止条例にも違反するおそれがあります。
神奈川県の定める神奈川県迷惑行為防止条例の場合、
・公共の場所や公共の乗り物の中で
・下着や服で隠された部分を見る、あるいはカメラなどを差し向ける行為
あるいは
・人を羞恥、あるいは人が不安を覚える方法で
・更衣室やトイレなどの衣服等を一部でも着けないでいるような場所において
・覗き見たり撮影したりする行為
が対象です。
【ケースの盗撮について】
ケースの場合、トイレという性器や肛門、臀部といった「人の性的な部位」を撮影する行為ですので、性的姿態等撮影罪に問われる可能性があります。
また、駅構内のトイレという、通常衣服等の一部を着けないでいるような場所にいる人の姿態を撮影する行為ですので、神奈川県迷惑行為防止条例にも違反することが考えられます。
1つの行為が2つ以上の罪に当たる場合は、いずれかの罪で処理されることになりますが、その場合は観念的競合といってより重い罪で処理されることになるため、性的姿態等撮影罪の量刑である3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処される可能性があります。
但し、実務では、被害者が特定されていない事件の場合、「正当な理由」があるのか否か確認できないとして、性的姿態等撮影罪ではなく神奈川県迷惑行為防止条例違反で処理することが考えられます。
例えば、Vさんがトイレの掃除などのために個室に入った人で、盗撮された被害者が特定されない場合など、
また、トイレに侵入したことによる建造物侵入罪の成立も検討されます。
【盗撮事件での弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに盗撮事件の弁護活動を数多く経験してきました。
主たる弁護活動としては、
・身柄解放活動
・不起訴や減刑を求める弁護活動
が挙げられます。
前者について、盗撮事件の場合は被疑者が逮捕される場合があります。
とりわけ、加害者が被害者の名前や連絡先を知っている場合などで、身体拘束しなければ被害者に接触して口止めなどをしてしまう恐れがあるとして、逮捕・勾留に踏み切ることが考えられます。
弁護士としては、家族の監督のもと、勾留の必要性がないことを主張して、勾留の回避・勾留決定の取消しや破棄を求める弁護活動が必要になります。
後者について、盗撮事件の場合は被害者がいます。
被害者が特定している場合、被害者に対し謝罪と賠償を行う示談交渉が必要不可欠になるでしょう。
また、窃視症の恐れがある場合には再犯防止のため依存症の専門医等の診断を勧めたり、家族全員で再犯を防ぐため相談する時間を設けて頂くなど、様々な対応が必要です。
神奈川県相模原市緑区にて、家族がトイレに侵入して盗撮事件を起こしてしまい、性的姿態等撮影罪や神奈川県迷惑行為防止条例違反で逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまった場合を想定―痴漢で問題となる罪と略式手続について
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまった場合を想定―痴漢で問題となる罪と略式手続について

神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて痴漢事件を起こしてしまったという架空の事例に沿って、痴漢事件で問題となる罪と略式手続について検討します。
【ケース】
神奈川県横浜市保土ヶ谷区在住のAさんは、横浜市保土ヶ谷区の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、横浜市保土ヶ谷区を走行するバス車内にて、右前に立っていたVさんの臀部(お尻)に右手で触るという痴漢行為をしました。
Vさんはすぐに運転手に被害を申告し、Aさんは通報を受けて臨場した横浜市保土ヶ谷区を管轄する保土ヶ谷警察署の警察官によって捜査されることになりました。
Aさんはインターネットなどで痴漢事件の手続の流れについて調べたところ、略式手続の可能性があるという記事を目にしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【横浜市保土ヶ谷区での痴漢事件について】
今回Aさんが行った、Vさんの臀部に触れるという行為は、俗に痴漢と呼ばれ各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反することとなります。
ケースでは横浜市保土ヶ谷区での事件を想定しているため、下記の神奈川県迷惑行為防止条例が問題となります。
神奈川県迷惑行為防止条例3条1項 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
1号 衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から、又は直接に人の身体に触れること。
罰条:「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(同条例15条1項)
【略式手続とは】
通常の刑事手続では、検察官が裁判所に被疑者を起訴をし、起訴された被疑者は被告人という立場になり、裁判所の法廷で裁判が行われ判決が言い渡されます。
しかし、比較的軽微な事件(100万円以下の罰金又は科料に相当する事件)の場合、通常の手続を簡略化した略式起訴が行われる場合があります。
検察官が略式起訴を決め、被疑者の異議がなかった場合、検察官は簡易裁判所に書類を送り、書面にて処分を下します。
公開の裁判等は行われません。
略式起訴は通常の刑事手続きに比べ、公開の裁判を受けずに済み、その場合に必要な弁護士費用等の負担もなくなるため、被疑者・被告人にとって有利であると考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの痴漢事件に携わってきました。
神奈川県横浜市保土ヶ谷区にて、痴漢などの刑事事件を起こしてしまい略式手続の可能性がある方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?
架空の事例を用いて検討―神奈川県茅ケ崎市にて未成年の児童に対してお金を渡して性行為をしたらどうなる?

18歳未満の児童にお金を渡して性行為をしたことで問題となる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県茅ケ崎市在住のAさんは、茅ケ崎市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは事件当日、SNSで知り合った16歳のVさんと茅ケ崎市内で落ち合い、ホテルにて2万円を渡して性行為をしました。
その後ホテルを出たAさんとVさんですが、パトロール中の茅ケ崎警察署の警察官に職務質問を受け、児童買春の事実が発覚しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童買春の罪】
令和5年の改正刑法により、いわゆる性同意年齢の引き上げが行われ、16歳未満の児童との性行為は原則として不同意性交罪として処罰されることになりました。
また、16歳・17歳に対して性行為等をした場合
・児童や保護者に対して対価を渡していた場合には児童買春の罪に
・それ以外の結婚を前提にしていない性行為については各都道府県の定める青少年保護育成条例違反(今回のケースであれば神奈川県青少年保護育成条例違反)に
該当するとして捜査され処罰されることが考えられます。
今回のAさんの事例では、16歳の児童Vさんに対して2万円の対価を渡して性行為をしているため、児童買春の罪に問われます。
条文は以下のとおりです。
児童買春、児童ポルノ処罰法2条2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1号 児童
2号 (略)
3号 (略)
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童買春をはじめとした性犯罪事件を担当してきました。
児童買春は厳密には被害者のいない事件とされる事件ですが、児童やその保護者に対し迷惑をかけたことへの謝罪と弁済を行う示談交渉を行うことで、不起訴処分となる事案もあります。
また、贖罪寄附の活用などが功を奏する事例もあります。
早期に弁護士に相談し適切な弁護活動を受けることが処分に影響することもあるため、神奈川県茅ケ崎市にて児童買春事件を起こしてしまった場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ
神奈川県相模原市にて児童ポルノ所持事件で捜査されたという架空の事例について検討するブログ

神奈川県相模原市にて、児童ポルノ所持が発覚したという架空の事例を前提に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県相模原市在住のAさんは、ある朝、突然自宅に来た警察官に「児童ポルノ所持の事件で令状を持ってきているから部屋の中を見せてください」と言われました。
Aさんが鍵を開けたところ、相模原市内の警察官数名が部屋に入って、スマートフォンやパソコンの場所を示すよう言われ、「これは児童ポルノ所持が疑われる証拠品として押収します」と言われました。
今後自分がどのような状況になるか分からなかったAさんは、刑事事件を専門とする弁護士に、無料法律相談を受けることにしました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童ポルノ所持で問題となる罪】
今回問題となったのは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」いわゆる児童買春・児童ポルノ処罰法の条文です。
児童買春・児童ポルノ処罰法では、18歳未満を児童とし、児童ポルノについて以下のとおり定義しています。
児童買春・児童ポルノ処罰法2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
Aさんの事例では、インターネット上にアップロードされていた児童の性的な動画・画像を「電磁的記録」としてダウンロードし、自身のHDDに記録しているため、児童ポルノ所持の罪で捜査を受けました。
児童ポルノ所持の事例は、サイバーパトロールなどでダウンロードの形跡を見つけ出して捜査が開始される場合、業者が摘発されて業者のリストやクレジットカード情報などから芋づる式に捜査される場合、別の事件を起こしてしまいスマートフォンを押収されその中に児童ポルノに該当する動画・画像が見つかった場合等、事件が発覚する経緯(事件の端緒)は様々です。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、これまでに数多くの児童ポルノ所持事件を扱ってきました。
児童ポルノ所持で捜査を受けている方、自首を検討されている方や、家族が児童ポルノ所持で逮捕されてしまった方は、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料で法律相談を受けることができます。
家族が逮捕・勾留されている場合はこちら。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県横浜市中区のインターネットカフェで睡眠作用のある薬物を飲料に混ぜて性交等をしたという報道について検討
神奈川県横浜市中区のインターネットカフェで睡眠作用のある薬物を飲料に混ぜて性交等をしたという報道について検討

横浜市中区にて、インターネットカフェで被害女性に対し睡眠薬のようなものを用いて眠らせた隙に性交等に及んだ男性が逮捕されたという事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【報道】
神奈川県警伊勢佐木署は3日、準強制性交の疑いで、中国籍で住所不定、職業不詳の男(29)を逮捕した。
逮捕容疑は、昨年1月22日午後10時20分ごろから同23日午前5時50分ごろまでの間、横浜市中区のインターネットカフェで、意識もうろう状態だった20代の会社員女性に性的暴行をした、としている。男は「覚えていない」などと供述している。
署によると、同市西区の飲食店で女性に睡眠作用のある薬物を飲料水に混ぜて飲ませ、意識もうろうの状態にし、インターネットカフェに連れ込んだとみられる。2人はSNS(交流サイト)で知り合ったばかりだった。女性が被害届を出し、インターネットカフェの利用履歴やSNSなどから男が浮上した。
<神奈川新聞「横浜のネットカフェで女性に性的暴行…容疑で逮捕の29歳「覚えていない」」2024年4月3日(水)23:08配信>
【睡眠薬を飲ませて被害者を眠らせ性的暴行を加えた場合に成立する罪】
今回の報道事例によると、捜査機関は
①被害者に睡眠作用のある薬を飲ませた
②意識が朦朧としていた間に性行為をした
という嫌疑をかけているようです。
■①傷害罪の成立
まず、①について、無断で睡眠作用のある薬を飲ませる行為は、傷害罪に該当します。
条文は以下のとおりです。
刑法204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、被害者の身体を傷害した場合に成立する罪です。
睡眠作用のある薬物を飲ませる行為は、適量を守った場合、効果が限定的でいずれ作用がなくなる(目が覚める)と考えられます。
しかし、傷害罪の言う傷害とは「他人の身体に対する暴行により…健康状態の不良な変更を惹起(引き起こす)ことをいう」とされています。(大判明45・6・20)
被害者を眠った状態にする行為は、健康状態の不良な変更を引き起こす行為であると言えますので、傷害罪にあたると考えられます。
■②不同意性交罪・準強制性交罪の成立
次に、①の状況で意識が朦朧としている女性に対し、性行為をしている点が問題となります。
報道によると、男性は準強制性交罪で逮捕されています。
≪※法改正前≫
刑法177条 13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。(略)
刑法178条2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
今回の男性が逮捕された準強制性交罪は、令和5年の刑法改正以前の罪名です。
刑事事件は、刑事不遡及の原則といって法律が制定される以前の行為を事後法で処罰することはできないとされています。
今回の場合、事件が令和5年1月22日と、2023年(令和5年)6月16日の刑法改正以前の事件であり、被害者を睡眠作用のある薬で眠らせることで「心神を喪失」させて性交等をしたとされているため、この罪で逮捕されたと考えられます。
【傷害罪・不同意わいせつ罪は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部へ】
加害者が被害者の連絡先を知っている場合、接触する可能性が高く証拠隠滅のおそれがあるとして身体拘束のリスクが高くなります。
また、今回の報道事例の場合、被害者を眠らせてその隙に性交等しているという犯行態様が悪質な点から、実刑判決を言い渡される可能性もあるとして、逃亡の恐れがあり勾留の必要性があると評価されることも考えられます。
弁護士は、事件の性質に即して身体拘束の可能性や釈放・保釈されるタイミング、必要な弁護活動について状況に即して検討し説明することが求められます。
神奈川県横浜市中区にて、家族が被害者に睡眠作用のある薬を飲ませ、その隙に性交等したことで、傷害罪や準強制性交罪・不同意性交等罪に問われている場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討
不同意わいせつ事件でいわゆる再逮捕をされたら?神奈川県小田原市での架空の事例を通じて検討

記事では、神奈川県小田原市にて不同意わいせつ事件を繰り返していた男性が逮捕され、その後再逮捕されたという架空の事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県小田原市在住のAさんは、小田原市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは、性的欲求を満たす目的で、深夜に小田原市内をうろつき、歩いている女性を探して1人であることを確認したうえで被害者の後ろから突然抱きつき、胸を揉みしだくなどのわいせつ行為を繰り返しました。
小田原市内を管轄する小田原警察署の警察官は、複数人の被害者による被害申告を踏まえ、捜査した結果Aさんによる犯行であるという裏付けが取れたため、Aさんを不同意わいせつ罪で通常逮捕しました。
Aさんの担当弁護士は、Aさんの家族に対し、Aさんは再逮捕される可能性が高いため身体拘束の期間は長期に亘ると説明しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【不同意わいせつ事件について】
令和5年6月16日の改正刑法により、従来「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」と称されていた罪が「不同意わいせつ罪」と変わりました。
条文は以下のとおりです。
刑法176条1項 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
1号 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
2号 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
3号 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
4号 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
5号 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
6号 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
7号 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
8号 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2項 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3項 16歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第1項と同様とする。
法改正以前の刑法では、強制わいせつ罪の定義は「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者」と「13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者」としていました。
暴行又は脅迫とされているため、暴力や暴言のほか、隙をついて行うわいせつ行為も暴行として処罰対象とされていました。
今回想定している事例では、Vさんは抵抗する隙があり、Aさんも暴行や脅迫を行っていないことから、強制わいせつ罪としては問えなかったと考えられます。
しかし不同意わいせつ罪の場合、176条1項5号で「同意しない意思を…表明し」「わいせつな行為をした者」としていることから、Aさんの行為は不同意わいせつ罪に当たると考えられます。
【再逮捕とは?】
我が国の刑事司法では、一罪一逮捕一勾留が原則です。
つまり、一つの犯罪に対して逮捕・勾留は一度限りであるべきだとされています。
そのため、1つの事件に対して被疑者を拘束できるのは逮捕から最大で23日で、担当する検察官はそれまでに被疑者を起訴して起訴後勾留に移るか、釈放しなければなりません。
但し、刑事訴訟法では以下のとおり規定されています。
刑事訴訟法198条1項 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円…以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
3項 検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。
この刑事訴訟法199条3項をみると、一度逮捕している被疑者に対し、同一の犯罪で改めて逮捕することを、刑事訴訟法は認めていることになります。
判例も、「同一の被疑事実によって被疑者を再度にわたり逮捕することも、相当の理由がある場合には許される。」としています。(東京高判昭48・10・16)
但し、判例が「相当の理由がある場合には」と限定的な言い方をしていることから、刑事訴訟法のいう再逮捕がなされることは極稀です。
ところで、テレビやインターネットニュースなどでしばし「神奈川県警小田原警察署は●●容疑者を不同意わいせつの疑いで再逮捕した」という報道をよく目にすることがあるかと思います。
これは、刑事訴訟法上の意味での再逮捕ではなく、別の事件で逮捕・勾留されていた被疑者を、他の事件で逮捕した場合を指すことがほとんどです。
上記のケースでも、こちらの意味で再逮捕という言葉を用いました。
つまり、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をXの事件で逮捕することが本来の刑事訴訟法が想定している再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則の例外と言えますが、Xの事件で逮捕・勾留していた被疑者をYの事件で逮捕することが一般的に言われる再逮捕で、これは一罪一逮捕一勾留の原則に反しません。
再逮捕が、刑事訴訟法上の意味であるか一般的な意味であるかは、極めて重要です。
【いわゆる再逮捕されそうな場合はすぐに弁護士に相談を】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、ケースのように余罪と呼ばれる別の犯罪を多数抱えていて今後再逮捕が複数回予定されているという事案をこれまでに多数扱ってきました。
基本的に、一般的な意味での再逮捕は法律上避けては通れません。
しかし、弁護士は捜査機関(警察官・検察官)とも協議し乍ら、被疑者の捜査に協力しつつ早期の身柄解放を求めます。
神奈川県小田原市にて、家族が不同意わいせつ事件を起こしてしまい逮捕され、いわゆる余罪での再逮捕が見込まれる場合、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県大和市でストーカー行為をしたらどうなる?フィクション事例を通じて成立する罪と弁護活動について検討するブログ
神奈川県大和市でストーカー行為をしたらどうなる?フィクション事例を通じて成立する罪と弁護活動について検討するブログ

ストーカーが倫理的に問題であることはご承知のとおりですが、法的にも禁止されていて違反した場合には刑事罰が科せられることになります。
ストーカー規制法はどのような行為を禁止し処罰するのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が検討します。
【ケース】
神奈川県大和市在住のAさんは、大和市内の会社に勤める会社員です。
ある日、Aさんの家に大和市内を管轄する大和警察署の警察官が自宅に来て、Aさんをストーカー規制法違反で通常逮捕しました。
Aさんの家族はAさんが逮捕された一部始終を見ていて、どのようにすれば良いか分からず、すぐに弁護士に初回接見を依頼しました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【ストーカー規制法の目的と定義】
「ストーカー行為等の規制等に関する法律(略してストーカー規制法)」では、法律の目的として、「この法律は、ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的とする。」と規定しております。
犯行は、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」が必要となります。
「つきまとい等」は、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいいます。
1 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その現に所在する場所若しくは通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
3 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
5 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、文書を送付し、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
6 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
7 その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。
8 その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。
「位置情報無承諾取得等」とは、上記目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、その承諾を得ないで、相手の位置情報を取得したり、位置情報が分かる道具を相手に取り付けさせたりすることをいいます。
相手のGPS情報を取得したり、GPS機器を相手に取り付けたりすることをいいます。
「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等を反復してすることをいいます。
つきまとい等に関して、第1号から第4号までと、第5号の電子メールの送信等に係る部分の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限ります。
何人も、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をして、その相手方に身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせてはなりません。
【ストーカー規制法における警告】
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長は、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をされたとして当該つきまとい等又は位置情報無承諾取得等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、更に反復して当該行為をしてはならない旨を「警告」することができます。
【ストーカー規制法における禁止命令等】
都道府県公安委員会は、違反する行為があった場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、その相手方の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、次に掲げる事項を命ずる「禁止命令等」をすることができます。
1 更に反復して当該行為をしてはならないこと。
2 更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
原則として聴聞を行わなければなりません。
禁止命令等の効力は、禁止命令等をした日から起算して1年です。
期間は1年ごとに延長することができます。
【ストーカー行為等での罰条】
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処されることになります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、つきまとい等又は位置情報無承諾取得等をすることにより、ストーカー行為をした者も、同様となります。
更に反復してつきまとい等又は位置情報無承諾取得等をしてはならないことの禁止命令等に違反して、ストーカー以外の行為をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになります。
【ストーカー規制法違反での弁護活動】
ストーカー規制法違反では、ストーカーされた側である被害者の意向が重要になります。
被害者の中には、加害者がまた接触を試みて来るのではないかと不安に思っている場合が少なくありません。
担当する弁護士は、被害者に対し、丁寧に説明を繰り返す必要があります。
被害者の意向次第で示談交渉を行うことになりますが、示談交渉では、被害者が二度と加害者に接触しないよう、
・加害者は被害者の連絡先を削除し連絡や接触をしない
・被害者の転居費用を負担する
・加害者が特定の場所(被害者の生活圏)に立ち寄らない
といった提案を行い、被害者に安心して頂く必要があります。
仮にストーカーが誤解であり被疑者が罪を否定している場合には、捜査機関による取調べや捜査を注視し、どのような証拠を以てストーカーを疑っているのか探り、不起訴(嫌疑不十分・嫌疑なし)を求める必要があります。
神奈川県大和市にて、家族がストーカー規制法違反で通常逮捕された場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。
神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討
神奈川県海老名市にて児童ポルノ所持事件で逮捕された事例を想定して弁護活動について検討

神奈川県海老名市にて発生した児童ポルノ所持で逮捕された事例を想定して、弁護活動について検討します。
【ケース】
神奈川県海老名市在住のAさんは、海老名市内の会社に勤める会社員です。
AさんはSNSを使って性的な動画や画像を集めていたところ、Vさんの「5000円送ってくれたら性的な動画を送る」旨の投稿を見つけ、個人間でやり取りをするダイレクトメッセージにて連絡を取り始めました。
Vさんのプロフィールには16歳であることを示唆する表示がありました。
AさんはVさんに性的な、電子マネーで金を支払い性的な画像を送るよう連絡しました。
後日、Aさんは逮捕され、海老名市内にある海老名警察署に連行されました。
≪ケースはすべてフィクションです。≫
【児童ポルノの所持について】
18歳未満の児童の性的な動画や画像を所持する行為は、児童ポルノ所持に該当します。
条文は以下のとおりです。
児童買春・児童ポルノ処罰法
2条3項 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録…に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
7条1項 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者…は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。(以下略)
【捜査の端緒とは】
新聞やテレビ、ネットニュース等を通じ、日々多くの刑事事件を目にするきっかけがあると思います。
捜査を最初に担当するのはほとんどの場合、警察官です。
しかし、警察官がすべての刑事事件を目撃して事件化しているわけではありません。
この、警察官などの捜査機関が捜査のきっかけを「捜査の端緒」と呼びます。
警視庁『令和4年の犯罪』の表を基にすると、主に以下のような捜査の端緒が確認できます。(総数は601,331件)
・告訴-告発(約0.007%) 例えば、被害者が刑事告訴した場合
・被害届等(87.75%) 例えば、被害者が被害届を提出した場合
・第三者からの届出(0.018%) 例えば、目撃者や警備会社などからの通報
・常人逮捕同行(0.001%) いわゆる私人逮捕
・119番転送(0.001%) 例えば、119番通報を受けた消防指令室が刑事事件の可能性があると判断して通報
・他機関からの引継ぎ(0.001%)
・警察活動等(0.081%)
・自首等(0.002%)
このように、全体の9割近くが被害届や刑事告訴・告発といったきっかけで捜査が開始していることが分かります。
【児童ポルノ所持における捜査の端緒】
前章では刑事事件全般での捜査の端緒について見ましたが、児童ポルノ所持の場合の捜査の端緒の場合はどのようなものが考えられるか、検討します。
前出のデータでは詳細が読み解けないものの、主に
①サイバーパトロール
②業者の摘発
③被疑者が別の事件で捜査されスマートフォン・パソコン等のデータを解析して発覚
④提供した児童が検挙・補導され、その送受信データで発覚
が考えられます。
①について
例えば、SNSを通じてやり取りをする場合などで考えられます。
主に隠語を使って行われているようですが、サイバーパトロールの担当者はそれらの文言を検索してやり取りを確認し、児童ポルノの所持等が疑われる場合には捜査します。
また、動画等の共有ソフト・アプリを使って児童ポルノを所持するケースもあります。
②について
①に被る部分がありますが、業者の摘発による捜査の端緒が考えられます。
数年前、DVDや動画データを販売していた業者が検挙され、立場ある人を含め様々な被疑者が児童ポルノの所持嫌疑で検挙された事件がありました。
特に児童ポルノデータを販売する場合、クレジットカードや電子決済のデータやメール・掲示板などでのやり取りが残るため、それらの情報をもとに検挙にされることになります。
③について
昨今の刑事事件では、性犯罪に限らずほぼすべての事件で、スマートフォンやパソコン等の電子端末のデータの提出を求められたり、押収されたりします。
それらのデータを解析した際に、児童ポルノのデータを所持していることが発覚し、検挙に至るケースが少なくありません。
④について
児童ポルノは業者等から購入したりアップされているデータをダウンロードしたりする場合だけでなく、児童個人から直接データを受け取る場合があります。
その児童が深夜徘徊などで検挙された場合などで、そのスマートフォンのデータを確認されることで児童ポルノを受け取った相手の情報が分かる場合が考えられます。
【弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部の紹介】
これまでに述べてきたとおり、児童ポルノ所持の場合は捜査の端緒が様々あり、ある日突然警察官から連絡が来たり逮捕されたりする可能性があります。
児童ポルノ所持で捜査される可能性がある場合、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
当事務所の弁護士は、児童ポルノの所持を含めて数多くの性犯罪事件で弁護活動を行ってきました。
児童ポルノ所持の事件は、事件の件数や前科・前歴の有無等により、検察官が不起訴・略式起訴・起訴のどれを選択するか検討することが考えられます。
弁護士としては、例えば直接の被害者がいない事件ではあるものの児童が特定されている場合、児童・保護者に対して謝罪等をすることが考えられます。
所持したデータが児童ポルノである認識がなかった場合には、取調べでの対応も重要になります。
神奈川県海老名市にて、児童ポルノ所持の嫌疑で捜査を受けている方、家族が児童ポルノ所持の嫌疑で逮捕されたという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 横浜支部は、神奈川県全域、東京23区、多摩地域、山梨県、静岡県を対象に、刑事事件・少年事件に特化した法律サービスを提供しています。
逮捕・勾留の阻止や不起訴の獲得など、多数の実績を持つ弁護士が、依頼者様に寄り添いながら最善の解決を目指します。
無料法律相談・初回接見サービスは24時間受付、土日祝日も即日対応をしており、迅速な対応が可能な体制をとっています。また、オンライン相談や電話相談も行っており、遠方の方やご来所が難しい方にも対応しています。ぜひご相談ください。