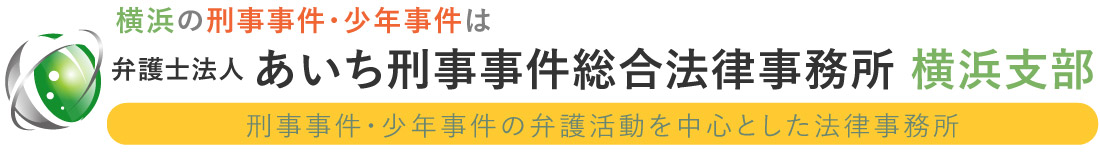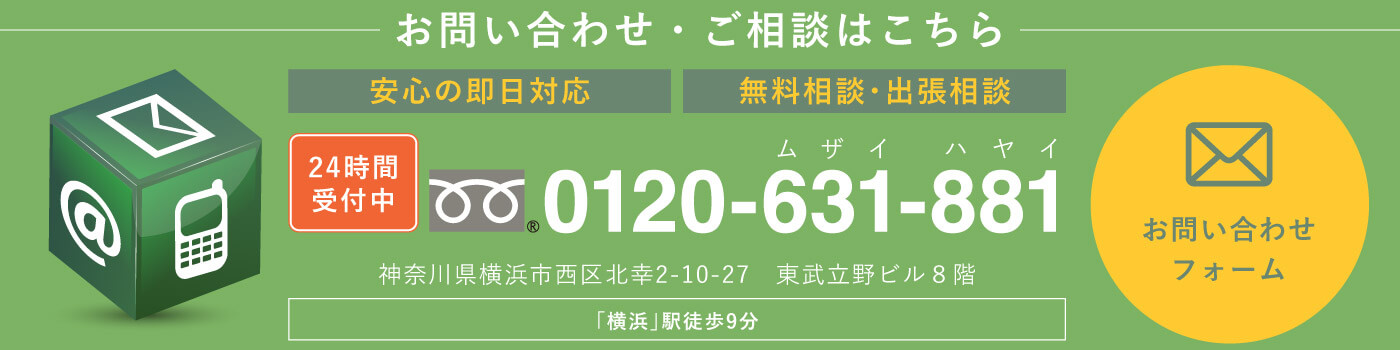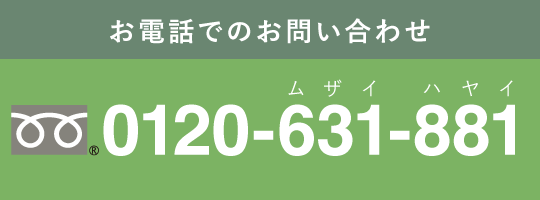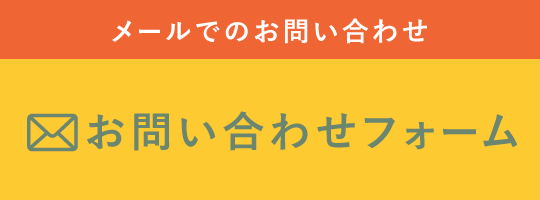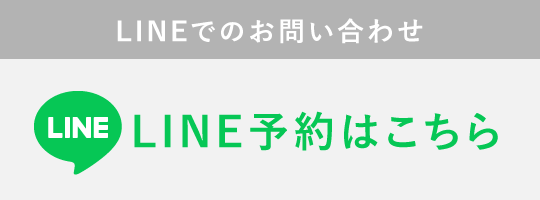Author Archive
【報道解説】神奈川県横浜市緑区の職場内トラブルの傷害罪で逮捕
【報道解説】神奈川県横浜市緑区の職場内トラブルの傷害罪で逮捕

職場内トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件概要】
神奈川県在住の会社員男性A(36歳)は、神奈川県横浜市緑区所在の勤務先の同僚会社員男性V(32歳)の頭部を空き瓶で殴って頭部挫創の傷害を負わせたとして、傷害罪の疑いで逮捕されました。
傷害を負ったVが、Aの犯行翌日に緑警察署に被害届を提出し、捜査がAの逮捕に至りました。
緑警察の調べでは、AはVが仕事中にミスをしたことに腹を立て暴行に及んだと動機を語っており、Aは逮捕容疑を認めています。
(令和5年1月25日の「HBC北海道放送ニュース」の記事をもとに、一部事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪】
傷害罪を規定する刑法第204条は、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。」としています。
刑法において、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯と言われています。
結果的加重犯とは、一つの違法な行為を行い、結果が生じなければ軽い方の罪で処罰し、結果が生じた場合には重い方の罪で処罰するものをいいます。
暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
他方、暴行行為を加えた結果、被害者が傷害を負った場合は、暴行罪の結果的加重犯として傷害罪が成立します。
上記刑事事件では、AがVの頭部を空き瓶で殴るという暴行行為を行い、その結果、頭部挫創という傷害が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【傷害罪の刑事弁護活動】
傷害罪や暴行罪といった暴力犯罪で軽い処罰を求めるためには、示談を締結することが刑事弁護活動で最も重要です。
被疑者が被害者に対し誠意を持って謝罪をして当事者間の問題解決(示談)に至れば、検察官が起訴することなく事件を終わらせる(不起訴)判断をする可能性が高まります。
ただ、被害者の怒りや被害の程度など、様々な事情から、示談が必ずしも円滑に進むとは限りません。
被害者が示談に応じない、あるいは、様々な示談条件を提示してくる等、示談交渉が難航する場合もあり得ますので、刑事事件の示談交渉の経験豊富な刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼することを強くお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪の示談交渉を数多く経験し、不起訴処分を獲得した実績が多数あります。
ご家族が傷害罪等の暴力事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご検討ください。
【報道解説】神奈川県相模原市で強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判の手続き
【報道解説】神奈川県相模原市で強盗致傷罪で逮捕 裁判員裁判の手続き

金銭を奪うために加えた暴行によって相手方を怪我をさせたことにより、強盗罪の疑いで逮捕された刑事事件例と裁判員裁判の概要について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「女性になりすましてSNSで呼び出した高校生に暴行を加え、金を奪おうとした疑いで、21歳の男ら2人が逮捕された。
A容疑者(21)らは2022年3月、神奈川県相模原市の路上で、男子高校生に『金を出せ』と脅して暴行を加え、けがをさせた疑いが持たれている。
A容疑者らは、SNSで若い女性になりすまし、高校生を呼び出していたという。」
(令和4年5月24日にFNNプライムオンラインにて配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです。)
【強盗致傷罪とは】
刑法240条は、強盗致傷罪について規定しています。
強盗致傷罪が成立するためには、「強盗が」、強盗の機会に、「人を負傷させた」という要件を充たす必要があります。
引用した報道では詳しい事実関係については明らかとなっていませんが、Aさんが高校生から金銭を奪うために加えた暴行が、高校生の反抗を抑圧する程度の暴行であれば、Aさんは「強盗」に当たることになるでしょう。
そして、そのような強盗の手段として用いられた暴行によって高校生が怪我をしていますので、Aさんは強盗の機会に「人を負傷させた」として強盗致傷罪の疑いで逮捕されたと考えられます。
なお、報道では「金を奪おうとした」との記載にとどまり、実際にAさんが金銭を高校生から奪ったかについては定かではありませんが、仮にAさんが金銭を奪っていなくとも、金銭を奪うために用いた暴行によって相手方を怪我をさせたのであれば、刑法243条が定める未遂罪は成立することはなく、強盗致傷罪の既遂が成立することになります。
強盗致傷罪の法定刑は、無期又は6年以上の懲役刑で、罰金刑が定められておらず、最も軽い刑で6年の懲役刑となっていますので、様々な犯罪について規定する刑法の中において、科される刑罰が大変重い犯罪です。
【強盗致傷罪で起訴された場合】
強盗致傷罪が起訴されると次に示すように通常の公判手続とは異なる点があります。
まず、強盗致傷罪のように法定刑で無期懲役が定められている事件が起訴された場合、その事件は、裁判員裁判の対象になります。
裁判員裁判制度は、職業裁判官と一緒に、国民の中から抽選で選ばれた人が裁判員として裁判に参加して、有罪・無罪の判断、有罪の場合の量刑をどうするかを決める裁判制度です。
裁判員裁判制度においては、量刑を判断にあたっては国民感情が反映されることになりますので、職業裁判官のみによって行われる通常の裁判に比べて、量刑が重くなる傾向があると言われています。
また、裁判員裁判の対象となる事件については、公判が開かれる前に公判前整理手続と呼ばれる手続が行われることになります。
公判前整理手続は、第1回公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人が事件の争点を明確にして、証拠の整理を行い、これからどのように審理を進めていくかという審理計画を作成することを目的とする手続ですが、審理計画の作成に時間がかかってしまい、結果として公判が長引いてしまうおそれがあります。
【強盗致傷罪の弁護活動】
このように強盗致傷罪は法定刑が重く重大な犯罪ですが、被害者に対する示談の有無によって、刑事処罰の可能性を低くする可能性が残されています。
事件を起訴するか否かを決定する権限は検察官にあり、検察官が事件を起訴するか否かの判断をするにあたっては、被害に遭われてしまった方の処罰感情を重視する傾向にあります。
そのため、検察官が起訴不起訴の判断を下すまでに、被害に遭われてしまった方に対して謝罪と被害の回復を行い、示談を締結することができれば、軽い処分となる可能性を高めることができます。
【軽い処分を目指したい方は】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱っている事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、被害者の方との示談交渉により、示談を締結することができ、強盗致傷罪から窃盗罪と傷害罪の2罪に分離させた結果、不起訴処分を獲得した経験のある弁護士が在籍しております。
強盗致傷罪を起こしてしまいお困りの方、強盗致傷罪について少しでも軽い処分を目指したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度御相談下さい。
司法試験受験生アルバイト求人募集2024
司法試験受験生アルバイト求人募集2024

アルバイト オフィス 法律事務所弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2024年(令和6年)度の司法試験受験生又は予備試験受験生を対象に、全国12都市にある各法律事務所の事務アルバイトを求人募集致します。司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方や、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件又は少年事件に興味のある司法試験・予備試験受験生は、うってつけの法律事務所アルバイト業務ですので是非ご応募下さい。
司法試験受験生アルバイト求人募集情報
あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。司法試験又は予備試験の勉強で学んだ法律知識が弁護士事務所でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。
【事務所概要】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な、刑事事件・少年事件及びその関連事件の弁護をメイン業務とする全国的刑事総合法律事務所です。著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件及びその関連業務をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱っています。全国12都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び事業部制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。また、更生支援、犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、当事者の支援や外国人問題に興味のある司法試験・予備試験受験生も歓迎しています。
【募集職種】
・事務アルバイト
・深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
・事務アルバイト:時給1300円+交通費
・深夜早朝アルバイト:時給1300円+深夜早朝割増(25%UP)+交通費
※時給は勤務地によって異なり、1000〜1300円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週1日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【執務環境】
・交通費支給
・各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
・PC、事務処理環境、インターネット等完備
・刑事事件、少年事件の専門性が高い職場
【勤務地】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部は、JR横浜駅近く(徒歩約9分)に事務所を構え、横浜市を中心に神奈川県及び関東地方一円の刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
横浜支部は2017年夏に開設されましたが、毎年およそ200件近い法律相談を承り、受任となった事件では、不起訴処分の獲得など多くの実績を挙げております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部では、被疑者・被告人の方の法的代理人として最大限の成果が上がるよう精力的に弁護活動を行うとともに、ご契約者様のご不安を解消するために逐次情報をご報告し、きめ細かい依頼者対応を心掛けております。
https://yokohama-keijibengosi.com
司法試験受験生アルバイト求人応募方法
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
【事例紹介】神奈川県横須賀市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕
【事例紹介】神奈川県横須賀市で交際相手宅への住居侵入罪で逮捕

交際相手または元交際相手とのトラブルによって相手宅へ押しかけてしまい住居侵入罪などの疑いで刑事事件化してしまった場合の、刑事事件の展開やその刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【刑事事件例】
神奈川県在住のアルバイト男性Aさんは、神奈川県横須賀市在住で交際していた女性Vから別れを切り出されたものの、AさんはVに対して未練があったため承服せず、メールやSNSを通じて「別れたくない」「もう一度話したい」等とメッセージを送っていました。
これに対し、Vは「もう二度と話したくない。今度連絡してきたら警察に通報する」と返事をしてきたため、AさんはVとの交際が終わったと理解し、V宅に置いてあったAさんの私物を回収しようとV宅へ行きました。
AさんはV宅のチャイムを鳴らしたものの、誰も出てこなかったため、自分の荷物だけ回収すれば問題ないだろうと思い、空いていた裏口のドアからV宅に侵入して自分の荷物を回収し帰宅しようとしました。
Aさんは、帰宅途中で神奈川県警横須賀警察署の警察官に職務質問を受け、自分がV宅に侵入した事実を認めたため、そのまま警察に連れていかれ、その後、住居侵入罪の疑いで逮捕されました。
(弊所に寄せられた法律相談を参考に、事実を一部改変したフィクションです。)
【交際相手との恋愛トラブル】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に寄せられる初回接見依頼の中で、恋人同士の喧嘩から派生したトラブルや、別れた後に復縁を迫ったりする等によりトラブルが生じ、刑事事件化する事例があります。
特に男性が女性の家やアパートに侵入したり、その際に家の一部を破損したり、女性の持ち物を盗んだとして、住居侵入罪や器物損壊罪、窃盗罪等の疑いで逮捕されたというケースが多くみられる傾向にあります。
このような事案では、表面上では上手く交際していた男女がトラブルになり、刑事事件化してしまったことに被疑者のご両親等がショックを受け、弁護士に事件を依頼することがあります。
また、別れた後に復縁を迫るパターンでは、被害者の加害者に対する嫌悪や恐怖感から、すぐに警察に通報し、加害者からの報復等を恐れた厳罰を求めるケースもしばしば見受けられます。
【住居侵入罪】
刑法第130条は、正当な理由なく、人の住居・人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入したり、退去要求を受けたにも関わらず退去しなかった場合には、3年以下の懲役または10万円以下の罰金を科すとしています。
行為の態様から区別して、前者を侵入罪、後者を不退去罪と言います。
実際に世の中で発生する犯罪(刑事事件)は、人の家や建物に侵入(住居新有罪・建造物侵入罪)して、財産を奪ったり(窃盗罪、強盗罪など)、無理矢理わいせつ行為に及んだり(強制わいせつ罪など)することが多く、このように、ある犯罪行為の手段・前提として行われる犯罪を牽連犯と呼び、このような複数の犯罪行為は、成立する最も重い法定刑により処断すると規定されています(刑法第54条第1項)。
ただ、場合によっては住居侵入罪・建造物侵入罪のみで刑事事件化する例もしばしば見受けられ、上記刑事事件例のように、元交際相手や友人等の家に家主に無断で侵入したような事案では、捜査機関は、既遂の住居侵入罪で迅速に逮捕し、その後余罪があるかどうかを調べていくというケースがあります。
特に、元交際相手のように複雑な人間関係にある者が被害者の場合、相手に対する憎しみや嫌がらせ等を目的に、住居侵入罪だけでなく、同時に窃盗罪や器物損壊罪が行われることもしばしば発生するため、罪が重くなることもあり得ます。
そして、元交際相手のような心理的な隔たりが大きい相手に対して、被疑者本人が謝罪したり被害弁償を行うことは事実上不可能である場合がほとんどであるため、このような住居侵入罪の刑事事件では、被害者との示談の締結によって不起訴処分を獲得するためにも、刑事事件の示談交渉の経験豊富な弁護士に依頼することを強くお勧め致します。
神奈川県横須賀市で、元交際相手宅への住居侵入罪で刑事事件化または逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
【事例解説】神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担 詐欺未遂で現行犯逮捕
【事例解説】神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担 詐欺未遂で現行犯逮捕

神奈川県厚木市で特殊詐欺に加担して、詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
「Aさんは、日払いのアルバイトをしようと思いSNSで検索したところ、書類の配達のバイトを見つけたので、応募して採用されました。
Aさんは、早速、電話で神奈川県厚木市にある高齢者宅に行って偽名を名乗って書類を受け取り、受け取った書類を所定の場所にいる担当者に渡すように指示されました。
Aさんは、この指示に従って、神奈川県厚木市にある家に向かい、呼び鈴を押して偽名を名乗ったところ、家から出てきた神奈川県警厚木署の警察官に詐欺未遂の現行犯で逮捕されました。
(弊所に寄せられた相談を参考に、事実を改変したフィクションです。)
【気づかない内に特殊詐欺に関わってしまう例】
事例のAさんのように書類の配送・配達のアルバイトだと思ってバイトを始めたころ、書類の受け取りが特殊詐欺の一部であったため、書類を受け取りに行ったら突然警察に逮捕されたという事件が珍しくありません。
事例のようなケースでは、概ね以下のような形で特殊詐欺が行われている場合が多いです。
・Aさんが書類を受け取る前に、別の人が特殊詐欺のターゲットにした高齢の被害者の方に、金融機関や公的機関の職員であると名乗って電話を架けている。
・電話では「お使いの口座が犯罪に使われている」や「還付金を受け取ることができる」などのウソの電話をして、被害者の方に暗証番号のメモとキャッシュカードや現金などの金目の物を封筒に入れさせて準備をさせる。
・金目の物が入った封筒を受け取り役のAさんが受け取る。
・封筒を受け取ったAさんが、別の場所に待機している大元の特殊詐欺の犯行グループの人に手渡す。
このような計画の元で行われる特殊詐欺では、被害者の方から書類を受け取る場面が、被害者の方と実際に対面することもあって、警察に逮捕されるリスクが一番高い場面であるといえます。
そのため、特殊詐欺を計画している大元の犯行グループは、書類の受け取り役をグループとは全く関係ないSNSでアルバイトとして募集してきた人物に担わせて、仮に書類の受け取り役が警察に逮捕されても、警察が大元の犯行グループまでたどり着かないように対策を立てています。
こうしたことに気が付かず、簡単にお金を稼ぐことができるアルバイトだと思って書類の受け取りをしてしまうと、詐欺の疑いで警察に逮捕されてしまう場合があります。
【書類を受け取っただけだから罪は軽い?】
刑法60条には「2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。」という規定があります。
これは、2人以上の人が共同して犯罪を実行した人を共同正犯として、他の人が行った行為についても、自分が行ったものとしてその責任を負うということを意味しています。
そのため、詐欺罪の共同正犯になってしまうと、たとえ書類の受け取りしかやっていなくても、他の人が行った嘘の電話をかける行為や最終的に金目の物を受け取る行為といった行為についても自分がやったものとして責任を負うことになります。
書類を受け取ったことで詐欺罪の共同正犯が成立するかは、実際にそのときにどういった認識があったかといった事情も非常に重要になりますので、書類の受け取り役が必ずしも詐欺罪の共同正犯になるという訳ではありません。
ただ、自宅訪問時に偽名を名乗るよう指示されたりと「これってもしかして詐欺じゃないのかな」と思うような事情があれば、詐欺罪の共同正犯が認められやすくなってしまうでしょう。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっていますので、詐欺罪の共同正犯になると、書類の受け取りしかしていなくても、10年以下の懲役刑が科される場合があります。
なお、事例のAさんは書類を受け取る前に上尾署の警察官に現行犯逮捕されていますから、実際に書類を受け取ってはいません。
そのため、Aさんには詐欺罪の既遂の共同正犯が成立する可能性はなく、詐欺罪の未遂の共同正犯が成立する可能性があるのみですが、詐欺罪の未遂といっても、法定刑は詐欺罪の既遂の場合と同じで10年以下の懲役刑となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。
【ご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は】
ご家族の中に、特殊詐欺に関わってしまったことで警察に詐欺の疑いで逮捕されてしまった方がいる場合には、弁護士に依頼して初回接見に行ってもらうことをお勧めします。
初回接見によって、弁護士が警察の留置場で拘束されているご家族の方から直接事件についてお話を聞くことができますので、事件の見通しや今後の手続の流れ、弁護士が取ることができる刑事弁護活動などについて知ることができるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県厚木市でご家族が特殊詐欺で警察に捕まってお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪
【報道解説】女性に抱きついて逮捕 暴行罪と不同意わいせつ罪

面識の無い女性に背後から抱きついたとして暴行罪の疑いで男性が逮捕された刑事事件例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「神奈川県逗子警察署は2日、暴行の疑いで、住所不定、無職の男(53)を逮捕した。
逮捕容疑は、1日午後2時40分ごろ、逗子市内の温浴施設内エレベーターで、同市内に住む従業員の女性(47)に背後から抱きついた、としている。
調べに対し『ハグしただけで暴行はしていない』と供述し、容疑を否認している
署によると、エレベーターには2人しかいなかった。
面識はなかったという。」
(令和4年10月2日にカナコロ:神奈川新聞社で配信された報道を参考に、場所等の事実を変更したフィクションです。)
【抱きつきは暴行罪になる?】
今回取りあげた報道では、逮捕された男性が警察の取り調べにおいて「ハグをしただけで暴行はしていない」と供述しているようです。
刑法208条が規定する暴行罪は、殴る蹴るなどの暴力行為をした場合に成立する犯罪だと思われている方がいるかもしれませんが、後ろから女性に抱きつく(ハグをする)行為は暴行罪に当たる行為になりますので、逮捕された男性には暴行罪が成立する可能性が高いと言えます。
ちなみに、暴行罪の法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金、又は拘留若しくは科料となっています。
【抱きつきは不同意わいせつ罪になる?】
報道を読んだ方の中には、抱きつく(ハグをする)行為は刑法176条の不同意わいせつ罪ではないのかと思われた方がいらっしゃるかもしれません。
確かに、見知らぬ女性に抱きつく(ハグをする)という行為は、場合によっては不同意わいせつ罪や、その未遂罪が成立する可能性があります。
令和5年7月13日の刑法改正によって、以前は「強制わいせつ罪」とされていた罪が「不同意わいせつ罪」と改定されました。
不同意わいせつ罪とは、次に掲げる行為や事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をすることを処罰するとしています。
具体的な行為や事由として、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害を生じさせること等」、「アルコールやは薬物を摂取等」、「睡眠その他の意識が明瞭でない状態の利用」、「同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない」、「予想と異なる事態に直面させて恐怖・驚愕させること」、「虐待に起因する心理的反応」、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益」の8項目が列挙されています。
不同意わいせつ罪が成立すると、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑が科されます。
そのため、被害者の反抗を著しく困難にする程度に抱きついたという場合は刑法176条の不同意わいせつ罪における「暴行」に当たることになりますので、そうして抱きついた上で、被害者の胸や下半身をまさぐったり、無理やりキスをしたりなどのわいせつな行為をした場合には、不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いと考えられます。
このように、抱きつき行為が具体的にどのような態様であったのか、抱きついた後に被害者に対して行った行為がどのようなものであったか、どのような目的で抱きついたのか等の事情によっては、不同意わいせつ罪や未遂罪が成立する可能性があります。
【抱きつきで刑事事件化したら】
取り上げた報道では、男性は暴行の疑いで逮捕されていますが、男性が女性に背後から抱きついたという事件ですので、今後の捜査では、男性が女性にわいせつな目的で抱きついたのか、抱きついた際に女性の身体のどこを触ったのかなどの抱きつき行為をしたときの具体的な状況などが詳しく捜査されることが予想されます。
抱きつき行為の目的や、その具体的な状況次第によっては、暴行事件ではなく、不同意わいせつ事件や未遂事件として手続きが進んでいく場合もあり得ます。
先ほど説明した暴行罪と不同意わいせつ罪の法定刑を比べるとわかるように、不同意わいせつ罪の法定刑には罰金が定められていませんので、仮に検察官が事件を不同意わいせつ事件として起訴した場合に必ず正式な裁判が開かれることになります。
従って、暴行罪よりも不同意わいせつ罪のほうが重い犯罪であるといえますので、事件が暴行事件として処理されるのか、不同意わいせつ事件として処理されるのかはその後の手続が大きく異なる可能性があります。
そのため警察の取り調べにおいては、取り調べを担当する警察官の誘導に引っかかって、抱きつき行為が不同意わいせつ罪に当たるようなものであったと虚偽の自白してしまわないよう、取調べには十分注意して臨む必要があります。
警察署の取調室という密室で、取調べのプロである警察官を相手に虚偽の自白を行わないようにするためには、事前に弁護士に相談して警察での取調べ等の対応についてアドバイスを得ておくことをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
人に抱き着いて暴行罪や不同意わいせつ罪等の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。
【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士
【報道解説】業務上横領罪で事件化する前に 示談交渉に強い弁護士

神奈川県で業務上横領の疑いで逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道紹介】
「会社の口座から自身の口座に振り込み入金し、現金を着服したとして、神奈川県警本部と山手署は1日、業務上横領の疑いで、麺類製造・販売会社元経理担当で自称パート従業員の男(48)=横浜市=を逮捕した。」
(令和5年2月2日に埼玉新聞で配信された報道より、事実を一部変更したフィクションです。)
【意外に罪が重い業務上横領罪】
今回取り上げた報道では、男性が業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪は刑法253条に規定する犯罪で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した」場合に成立する犯罪です。
業務上横領罪が成立する場合としては、会社から割り当てられた業務として会社の備品を管理する業務を担っていた人が管理している会社の備品を転売した場合や、経理として会社の口座を管理している人が会社の口座から自分の口座へと送金して会社の資金を着服した場合などが考えられます。
このような業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役刑となっています。
法定刑に罰金が定められていませんので、仮に検察官が業務上横領罪で起訴するという判断をした場合は、略式起訴することができず正式な裁判が開かれることになります。
【業務上横領罪が会社に発覚したら?】
会社の資金を着服してしまったなどの業務上横領罪に当たる行為をしてしまった場合は、弁護士に今後の対応についてご相談されることをお勧めします。
業務上横領罪については、まず最初に会社内部で調査が行われて、調査の結果、会社が業務上横領罪について刑事告訴をしたところで警察などの捜査機関が捜査に乗り出すという流れで刑事事件化することが多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部に寄せられる業務上横領の相談事例についても、まず会社側が業務上横領の事実を認識し、横領が疑われている方と会社側で話し合いを行い、横領した金額を返せば、会社側は被害届や刑事告訴を行わないと申し入れるケースが見受けられます。
そのため、業務上横領罪について会社が被害届や刑事告訴する前に、弁護士を通して会社に対して謝罪や横領金額の返金などの示談交渉をして、会社が謝罪と被害の弁済を受け入れてくれるといった形で会社と示談を締結することができれば、警察が業務上横領罪について捜査に乗り出す前に当事者間で事件を解決することができる場合があります。
また、被害を受けた会社側も、少しでも横領された金額が返金されることを望むことが多いので、横領を疑われている方の段階的な財産処分を通じて被害弁償をすることで、事実上の示談が成立することもあり得ます。
このように業務上横領罪を刑事事件化する前に当事者間で示談ができれば業務上横領罪の前科を付けずに事件を解決することができるでしょう。
そのような解決を目指すには、業務上横領罪が会社に発覚してから、少しでも早く弁護士に相談することが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県で業務上横領罪が会社に発覚してお困りの方や、業務上横領罪の前科を付けたくないとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部まで一度ご相談ください。
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕
【事例解説】大麻栽培の大麻取締法違反で逮捕

神奈川県茅ケ崎市の大麻栽培で大麻取締法違反で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【事例紹介】
神奈川県茅ケ崎市の自宅で営利目的に大麻草を栽培していたとして、中国人の留学生の男2人が逮捕されました。
大麻取締法違反の疑いで逮捕されたのは、茅ケ崎市に住む中国人の留学生A容疑者(23)ら2人です。
警察によりますと、2人は15日、茅ケ崎市内の自宅で、大麻草それぞれ1本を栽培した疑いが持たれています。
2人は容疑を否認しているということです。
2人の自宅からは大麻草の鉢や小分けにするための道具などが押収されていて、警察は2人が大麻を密売していた可能性があるとみて調べています。
(令和5年9月18日のテレ朝NEWSの記事を元に、場所等の事実を改変したフィクションです。)
【大麻栽培の罪と営利目的の加重】
大麻取締法では、大麻について所持していたり、譲り渡したり、逆に譲り受けたりといった、大麻に関係する様々な行為を規制の対象にしています。
このような大麻取締法で規制される行為のひとつには大麻を栽培した場合も含まれています。
具体的な規定を見てみますと、大麻取締法24条1項では、「大麻を、みだりに、栽培し…た者は、7年以下の懲役に処する」と規定しています。
また、大麻取締法24条2項では、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300百万円以下の罰金に処する」と規定されています。
【薬物犯罪の捜査の特徴】
上記刑事事件において、被疑者らは大麻取締法違反の疑いで逮捕されたと報道されましたが、おそらく、逮捕に引き続きさらに10間の身体拘束(勾留)が決まる可能性が高いと見込まれます。
勾留とは、被疑者が住所不定であったり、逃亡や、罪証隠滅(証拠隠滅)をする恐れが見込まれる場合に、検察官が請求し、裁判官が認めることで、10日間の身体拘束を決定する手続きを言います。
さらに、勾留の満期にあたり、さらに最大10日間の勾留延長が決定した場合、合計20日間の身体拘束となる可能性もあります。
大麻取締法違反の薬物犯罪では、薬物の売買等の犯行の広がりから、複数犯あるいは組織的な犯罪になる可能性が高く、口裏合わせ等による罪証隠滅が強く疑われる傾向があります。
また、仮に釈放してしまった場合、薬物は軽量で可燃性であるため、他の犯罪に比べて証拠隠滅が比較的容易とされています。
それゆえ、薬物犯罪は、一般的に罪証隠滅が強く疑われる性質があり、勾留が決定しやすい犯罪類型と言われています。
また、勾留が決定した場合、通常であれば、勾留された被疑者は家族等との面会が許されるのに対し、被疑者が逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があると判断した場合は、被疑者が弁護人以外の人と面会することをを禁止したり、弁護人以外の人と手紙のやり取りをすることを制限することができ(刑事訴訟法81条)、これを「接見等禁止」と呼ぶことがあります。
上記の薬物犯罪の共犯や組織犯罪に結びつく性質から、薬物犯罪の刑事事件では、一般的に、勾留決定にあたって接見等禁止決定が付くことが多いとされています。
【接見等禁止決定が付されている家族と面会したい方は】
接見等禁止決定が付されて長期間にわたって面会できないという状況は、身柄を拘束されているご本人様や、身柄が拘束されている被疑者のご家族様にとって、大変重い苦痛であると思います。
そのため、接見等禁止決定が付されて大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士に依頼されることをお勧めします。
接見等禁止決定が付されている場合、弁護士は、接見等禁止決定の全部または一部を解除するように裁判官に申立てることができます。
このような接見等禁止決定の全部または一部の解除決定は、刑事訴訟法上に具体的な規定が置かれているわけではありませんが、弁護士が裁判官に働きかけて、裁判官の職権の発動を促すという形になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所さいたま支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
神奈川県茅ケ崎市で大麻取締法違反の疑いで勾留されているご家族の方と面会できずにお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部まで一度ご相談ください。
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放
【報道解説】神奈川県横浜市戸塚区の電車内の乗客同士の喧嘩で傷害罪 現行犯逮捕で身柄解放

電車トラブルによる傷害罪の刑事事件とその弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【報道解説】
神奈川県在住の会社員男性A(25歳)は、会社帰りのJR東海道線の電車内で、同じ車両にいた会社員V(40歳)の顔を殴って鼻骨骨折させたとして、傷害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
神奈川県警戸塚警察署の調べでは、Aは電車内で座り込んでいたところ、Vに「電車内で座るな、邪魔だ」と言われ逆上し、Vに暴行を加えたとのことで、Aは逮捕容疑を認めている模様です。
(令和4年6月23日の神奈川新聞「カナコロ」の記事をもとに、犯行場所等の事実を変更したフィクションです。)
【傷害罪とは】
傷害罪は刑法第204条に規定されています。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立し、「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科されます。
刑法に規定する暴力犯罪において、傷害罪は、暴行罪の結果的加重犯と言われています。
つまり、暴行罪は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったとき」に成立し、その結果「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立することになります。
ここで言う「暴行」とは、「人の身体に対する不法な有形力の行使」とされており、上記刑事事件例のように、人の顔を殴るという行為は、明確に「暴行」に該当し、その結果鼻骨骨折という傷害の結果が生じているため、傷害罪が成立することになります。
【電車トラブルから発展した傷害罪】
本来、犯罪行為が行われたからといって、すべての犯罪を警察が逮捕権を行使する訳ではありません。
警察は、逮捕のような強制処分ではなく任意の方法で捜査を進めることが原則とされており、逮捕が必要な場合には、裁判所が逮捕を必要と判断し、逮捕を許可して逮捕状を発行することが必要とされています(通常逮捕)。
しかし、上記刑事事件例のように、電車トラブルによる傷害罪という事案では、多くの人の目の前で傷害罪という犯罪が行われるため、逮捕状の発行を必要としない「現行犯逮捕」される可能性が非常に高いと言えます。
電車トラブルによる傷害罪で現行犯逮捕されてしまうと、そのまま警察の留置場で身柄を拘束されることになるため、それ以後、会社や学校に行けなくなる等の社会的不利益が生じます。
【傷害罪の刑事弁護活動】
そのため、電車トラブルの傷害罪で現行犯逮捕された場合、まずは早期に身柄を解放してほしいというニーズが考えられます。
被疑者が逮捕されると、警察は事件を検察官に送致します。
検察官は、逮捕に引き続いて被疑者の身柄を最大10日間拘束する「勾留」の必要の有無を判断し、検察官が勾留請求してこれを裁判所が認めると勾留が決定していまいます。
さらに勾留の満期において、さらに最大10日間の勾留延長が可能であるため、被疑者は最大20日間勾留されることもあり得ます。
これだけ長期間身柄が拘束されると、会社を解雇されたり、会社を辞職せざるを得なくなったり、その他重い懲戒処分を受けたり、様々な生活に支障をきたすことになるでしょう。
このような逮捕事案では、逮捕された段階ですぐに刑事事件の経験豊富な弁護士に弁護を依頼し、勾留が決定されることを回避する活動をしてもらうことで、早期に身柄が解放できるよう手を打つことをお勧めします。
【傷害罪の刑事弁護活動】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪等の逮捕事案を数多く受任し、勾留阻止のための活動を数多く経験し、勾留阻止による早期釈放の実績を多数挙げております。
電車トラブルの傷害罪で逮捕されお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
【報道解説】神奈川県川崎市多摩区の不同意性交等罪の逮捕事件
【報道解説】神奈川県川崎市多摩区の不同意性交等罪の逮捕事件

不同意性交等罪の逮捕事案を紹介しつつ、その刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所横浜支部が解説します。
【報道事例】
令和5年7月14日、神奈川県川崎市で、知人の女性を暴行し同意なく性行為に及んだとして、不同意性交等罪の疑いで19歳の男子大学生が逮捕されました。
神奈川県警多摩警察署によりますと、男子大学生は、14日午後7時すぎ、川崎市多摩区内で、知人の10代女性が拒否しているにも関わらず暴行し、同意なく性行為に及んだ疑いが持たれています。
調べに対し、男子大学生は、「間違いありません」と容疑を認めているということです。
(令和5年7月15日に配信された「仙台放送」の記事を基に、場所等の事実を一部変更したフィクションです。)
【刑法改定:不同意性交等罪の新設】
令和5年7月13日をもって、「不同意性交等罪」が施行されました。
不同意性交等罪の新設の背景には、近年における性犯罪をめぐる状況に鑑み、構成要件の明確化と細分化を進め、以てこの種の性犯罪に適切に対処する必要があるとの理由に基づいています。
このたびの刑法改正により、旧刑法の「強制わいせつ罪」「準強制わいせつ罪」「強制性交等罪」「準強制性交等罪」を統合し、新法における「不同意わいせつ罪」および「不同意性交等罪」を規定することになりました。
あわせて、性犯罪についての公訴時効期間の延長や、被害者等の聴取結果を記録した録音・録画記録媒体に係る証拠能力の特則の新設なども盛り込まれています。
【不同意性交等罪とは】
本ブログでは、主に不同意性交等罪の構成要件と法定刑にしぼって解説します。
不同意性交等罪では、「次のような行為」等により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず処罰されることになります(刑法第177条第1項)。
「次のような行為」等を簡潔にまとめると、「暴行若しくは脅迫」、「心身の障害(おそれも含む)」、「アルコール若しくは薬物の摂取」、「睡眠その他の意識不明瞭状態」、「不同意を形成・表明するいとまがない」、「予想と異なる事態への恐怖・驚愕」「虐待に起因する心理的反応」、「経済的・社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること」の8項目が列挙されています。
改定前の強制性交等罪でも「暴行」もしくは「脅迫」が構成要件になっており、この「暴行」「脅迫」は、被害者の犯行を著しく困難にする程度のもので足り、犯行を抑圧する程度に達する必要は無いとされていました(最高裁判例)。
被害者の犯行を著しく困難にする程度とは、具体的には、犯行態様のほか、時間的・場所的状況、被害者の年齢や精神状態等を考慮して客観的に判断されるとされていました。
今回の刑法改正は、上記のような総合的判断から踏み込んで、より具体的な構成要件を提示することで処罰範囲の明確化を図るべく改定されたものと思われます。
不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑となっています。
【不同意強制性交等罪の刑事弁護】
今回の刑法改正によって不同意性交等罪が新設されましたが、従来の性犯罪に対する刑事弁護の原則どおり、前科が付くことを避けたい場合は、検察官に事件を起訴される前に被害者の方と示談を締結することが重要になります。
というのも、起訴前に被害者の方と示談を締結したという事実は、検察官が起訴をするかどうかの判断に当たって起訴を回避する判断に傾く考慮要素となるからです。
示談交渉は通常、被害者が成人であれば被害者本人と交渉を進めますが、被害者が未成年である場合は、被害者の保護者の方と示談交渉を行うことになります。
性犯罪全般の傾向として、被害者の方は、不安や恐怖に怯え、傷つけられた自尊心から犯人を許せないという処罰感情が強く、示談が難航することは珍しいことではありません。
しかし、刑事弁護の経験豊富な弁護士が、粘り強く謝罪や示談の条件を提示し、二度とこのような犯罪を起こさないと制約すること等を通じて、最終的に示談の締結に至る実績も多数ございます。
示談交渉は必ずしも決まった方法があるわけではなく、被害者の方が何を望んでいるのかを汲み取り、それに対して最適な問題解決案を提示することが最も重要ですので、示談締結の確率を少しでも上げたいと希望する方は、示談交渉の経験が豊富な弁護士に依頼されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所で、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。
不同意性交等罪の性犯罪で被害者の方との示談を考えている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談や初回接見サービスをご利用ください。